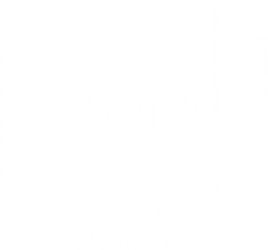一昨日、ヨラム・ハゾニー著「ナショナリズムの美徳」を紹介させていただきましたが、「難しい!」という反応を何人かからいただきました。でも、今後の世界を見る上でとっても大切なので、追加を書かせていただきます。
著者はユダヤ人ですが、イスラエルという国民国家の成り立ちを次のように描いています
ユダヤ人の多様な部族は、ユダヤ教と法律、ヘブライ語、そして何千年にもさかのぼり逆境に直面したときに団結した歴史を共有する。さらに、これらの部族が自発的に団結して、集合的自己決定を前進させるためにユダヤ人の国民国家を設立した……国家のシンボルと性格はユダヤ人というネイション(民族)とその宗教的伝統に由来しており…… (p193)
多くの人々が誤解していますが、イスラエル国民の中には、73%のユダヤ人、21%のアラブ人、6%のその他の人々が存在します。安息日を国全体で大切にするなど明らかにユダヤ教の習慣が国全体を覆っていますが、信教の自由は徹底されています。ほとんどのアラブ人はイスラム教を信じ、二千年来の固有の歴史を持つ独自のキリスト教の教派も存在します。
ユダヤ人は激しい迫害を受けて来た歴史から、国防意識が極めて高く、多くの国民はそれを当然の義務と考えています。
ハゾニー氏が強調しているのは、そのように人口の七割を超えるユダヤ人の独自性が守られ尊重される結果として、国の安全と平和が確保されるとということと、そのユダヤ人の団結が、自国に住むアラブ人への寛容を生み出しているということです。イスラエルに住むアラブ人は、ユダヤ国家の文化を受け入れ、徴兵を含む義務を果たすことで、彼らの生活と自由が保障されます。
今起こっている問題は、イスラエルという国を無くすることを悲願とするテロ集団との戦いであり、イスラエルという国の民族主義的な排他主義ではありません(ただ、誰の目にもイスラエルが過剰防衛にってパレスチナ難民を苦しめていることは明らかかと思います。それに対して私たちも声を上げるのは当然です)。
つまり、国民国家とは、その国の多数派である人々の価値観や文化が守られることで、互いへの信頼、国の安定が生まれ、その結果として異民族を受け入れる余裕が生まれるという考え方です。
ところが最近の欧米のリベラリズムの動きは、自分たちの固有の文化を中和化することで、文化や歴史を共有することから生まれる団結や信頼関係を失わせようとしていることが問題だというのです。
それはたとえば、オバマ大統領の時代に、「メリー・クリスマス」という代わりに「ハッピー・ホリデー」と言い合うことで信教の自由を表現しようというようなものです。それに対して、米国の保守的クリスチャンの反動が起こり、米国のキリスト教的な文化を守ろうという動きになりました。先日、米国でチャーリー・カーク氏という若者のクリスチャンリーダーが暗殺され、そこから若者の間に信仰のリバイバルが起きているという報道もあります。
米国には理想的なクリスチャンの国を作ろうとしたという文化的な背景があったと思われます。しかし、その中核の理念を否定してしまっては米国民として共有できる価値観が無くなります。問われているのは、中核的な文化的な価値観を守るということであり、決して少数派を排除するということではありません。
この日本にも共有できる歴史認識や価値観があります。たとえば日本人であれば、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の人格的特徴やそこから生まれた日本の統一の歴史を知っています。
また広島の原爆記念碑に、「安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから」と記されていることに違和感を覚える人は少ないと思います。しかし、国際的な標準からしたら、原爆を投下した米国を非難することばが記されてしかるべきとも言えます。ところが多くの日本人は、戦争自体が問題であったという見方をします。これも極めて日本人的な美徳と言えます。
私たちはそのような日本的なナショナリズムの美徳を尊重することによって、互いへの信頼と国民の一体感を保ち、結果として、異なった文化や言語を受け入れる余裕が生まれると言えましょう。
聖書では、すべての人々を無差別に平等に愛する「博愛」ではなく、「互いに愛し合う」という相互愛が説かれています。共有できる文化を大切にすることで互いへの愛が増し加わり、その互いへの信頼感から、異なった人々を受け入れる余裕が生まれるというのが、本書の核心のように思えます。
以下の詩篇85篇では、神への正直な不満を述べることで、神との信頼関係が築かれるという逆説的な祈りが描かれます。
詩篇85篇1–13節「神への賛美と懇願との関係」
この詩では1–3節に描かれた神のあわれみへの賛美と、4–7節の切羽詰まった懇願の不安が対照的です。それを過去と現在の対比と見る翻訳も多くありますが、ヘブル語には英語のような時制の区別はなく、外側から見るか内側から体験するかの視点の違いとも解釈できます。
ここでは、神の永遠のご性質とみわざを歌うことと、それに反しているように見える現実の内側からの民の心の叫びの対比が描かれていると思われます。
そして、神の永遠のあわれみの原則を知っているからこそ、今の気持ちを大胆に訴えることができるということこそ、詩篇の祈りの最大の魅力と言えましょう。
その反対に、親の顔色をいつも窺っているような子供は、自分の願いを大胆に訴えることができません。自分の気持ちをダイレクトに訴えると、かえって親の反発を招くと恐れるからです。
それで真実の親子関係のように、この詩では、「あなたは 御民の咎を担い すべての罪を おおってくださいます……燃える御怒りから身を引かれます」(2、3節) と、人間の罪に対して神ご自身が解決を示してくださるという永遠のご計画がまず歌われます。これこそ、神がご自身の御子を私たちの咎を担わせるためにお送りくださった十字架の愛です。
著者はそれを知りながら、敢えて現在の悲惨な状況下から、「私たちへの御怒りをやめてください あなたは とこしえに 私たちに怒られるのですか」と、子供のように訴えます (4、5節)。
著者は神の怒りの原因が民の罪にあること、また、神の怒りが「とこしえ」ではないことを理屈の上では分かっていますが、正直な今の気持ちとしては、神が「代々に至るまで 御怒りを引き延ばされる」(5節) ように感じられているからです。
それでなお、「あなたは帰って来て 私たちを生かしてくださらないのですか」(6節) と問いかけます。神はかつて、民の偶像礼拝の罪のために、エルサレム神殿を立ち去り、その結果、バビロン帝国が神殿を滅ぼしました。その因果関係を知っているからこそ、著者は、神の帰還の可能性を尋ねます。
そればかりか、なお大胆に、「お示しください。あなたの恵みを。お与えください。あなたの救いを」(7節) と訴えかけています。
8節からは、民に対する励ましが記されます。それは、「主は 御民に……平和を告げられ……御救いは主を恐れる者たちに近い」という主のご性質に希望を抱くからです。その上で、「恵みとまことは ともに会い 義と平和は口づけします」(10節) と印象的に歌われます。
11節に「まことは地から生え出で 義は天から見下ろし」とあるように、天からは「恵み」と「義」が「見下ろし」ます。「恵み」とはヘブル語のヘセド「変わらない愛」であり、「義」は神のご自身の契約に対する真実さで、このふたつは同じような意味があります。
それに対応するのが「まこと」と「平和」で、前者は「アーメン」と同根のことばで人に信頼を生み、後者は「平和」と同時に繁栄を意味し、それらが地から「生え出で」成長し、天と地が一つになるように「ともに会い」「口づけ」します。
祈りとは、主の永遠の愛を賛美しながらも、今感じて不安を、子供のように正直に、大胆に訴えることです。私たちはそのような神との対話を通して、主の「恵み(契約の愛)」と「義(真実)」に対応するこの地の「まこと」と「平和」の成長を期待できるのです。
【祈り】主よ、あなたの恵みと義のみわざに感謝します。しばしばそれを忘れて心が騒ぎますが、あなたがそれを受け入れ、この地に、まことと平和を成長させてくださいますように。