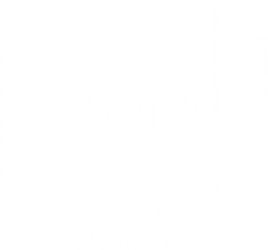本日の自民党総裁選で高市早苗氏が総裁に選ばれました。今後、日本で初めての女性の総理大臣になる可能性が高くなっています。これは日本が変わる大きなチャンスかもしれません。
彼女は何よりも日本の伝統と文化を大切にする保守的な信条の持ち主として有名な方です。小学校に入る前から以下の教育勅語を暗唱していましたし、これを現代の教育にも生かすべきと考えておられるようです。
指導者をあまり一面的に評価することを私たちは注意する必要があります。主ご自身がこの世の権威者を立てるというのが聖書の考え方ですから (ローマ13:1、2)、彼女の信条の美しい面を私たちは正しく評価する必要があります。しかし同時に、以下の教育勅語こそが第二次大戦前の日本の精神的な支柱となっていたことも忘れてはなりません。そこには日本の美しい伝統と同時に、首をかしげざるを得ないことも記されています。
以下は明治23年 (1890) に発布され、子どもたちに暗唱するように命じられた天皇のからの教育勅語の原文です
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス 爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ 是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン 斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ 明治二十三年十月三十日 御名御璽
教育勅語 現代語訳
私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。
あなたたち国民は、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は仲睦まじく協力しあい、友だちとはお互いに信じ合い、行動は慎み深く、皆に博愛の手を差し伸べ、学問を修め手に職を付け、それによって知能を更に開き起こし、徳と才能を磨き上げ、進んで公共の利益や世間のため人のため尽力し、いつも憲法を重んじ法律に従い、もし非常事態が生じたなら、正義心から勇気を持って公のため奉仕し、それによって永遠に続く皇室の繁栄に尽くしていくべきです。
これらのことは、単にあなた方が忠義心篤く、善良な国民であるというだけでなく、あなた方の祖先の遺した良き伝統を反映していくものでもあります。このような道は、実に我が皇室の祖先の御遺しになった教訓であり、その子孫と国民が共に守らなければならないことで、昔も今も変わらず、国の内外を問わず間違いのない道です。私は、あなた方国民と共にこの教えを胸中に銘記して守り、皆一致して立派な行いをしてゆくことを切に願っています。
以下の詩篇86篇ではダビデの嘆きと主への嘆願が歌われています。どんな忠君愛国の思想にもまさる歌を覚えたいものです。
詩篇86篇「私は苦しみ 貧しいのです」
この詩は第三巻(73–89篇)で唯一のダビデの作品です。この最初の原文は、「傾けてください。ヤハウェよ、あなたの耳を」という訴えから始まります。そして自分の状況を、「私は苦しみ 貧しいのです」と直接的に表現します。この部分は多くの英語訳では、I am poor and needy(私は貧しく乏しいのです)と訳しています。
さらに2節では「お守りください、私のたましいを」ということばから始まりますが、続くことばは、「私は敬虔な者です」とか、「私は誠実な者です」と訳すことができます。これは15節で「恵み」と訳されているヘブル語のヘセド(変わらない愛)と同じ語源のことばです。
著者は、自分の「誠実さ」が報われていない現実を訴えています。それは14節にあるように、「高ぶる者ども」「横暴な者の群れ」が、自分の「いのち」を奪おうと迫ってきている現実があるからです。
それで改めて著者は、神を「あなた」と呼びながら「あなたは私の神」と告白し、さらに「私はあなたに信頼します」(2節) と自分の意思を明確にします。
9節では、主こそが世界のすべての国々の創造主であり、すべての国々が主の「御前に来て 伏し拝み……御名をあがめます」と告白されますが、これは黙示録15章4節で引用される、偶像礼拝の強要に屈しなかった人々の賛美になります。これこそ主がアブラハムを召し、「地のすべての部族は、あなたによって祝福される」と約束されたことの成就であり、歴史のゴールです。
そして、著者は、「主よ、あなたの道を私に教えてください……私の心を一つにしてください」と祈ります (11節)。それはこの地の様々な誘惑や人間的な知恵に惑わされずに、自分の心がまっすぐに神に向かうようにとの願いです。その結果が、「心を尽くしてあなたに感謝」するという賛美につながるのです (12節)。
15節の主への告白は、モーセが心の頑ななイスラエルの民を導く不安の中で、主に、「あなたの栄光を私に見せてください」と大胆に願った際に、主がご自身を現わしてくださったことばそのものです (出エジプト34:6)。
その核心は、主が「あわれみ深く、情け深い神。怒るのに遅く 恵みとまことに富んでおられる」ということです。そして、ヨハネ福音書が神の御子イエスを、「ことばが人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た……この方は恵みとまことに満ちておられた」(1:14) と描いたのは、これを引用したものです。
たとえば、「父なる神」というときに、自分の父親のイメージを無意識に神に投影する人がいます。それはたとえば、子供の過ちをただ厳しく叱責する姿であったり、また心の動きに無関心に結果だけを評価する父であったります。そのイメージがこのみことばを通して正される必要があります。
16、17節では「御顔を私に向け 私をあわれんで……あなたのしもべに御力を与え……あなたのはしための子をお救いください。私に いつくしみのしるしを行ってください」と祈られます。これこそ、最初に自分の貧しさ、乏しさを告白したことに対する祈りの応答です。
特に「はしための子」という表現は珍しいもので、著者の徹底的な謙遜を現わします。自分の将来は、神からの与えられる「力」と「いつくしみのしるし」にかかっているとの告白です。自分の能力や知恵ではなく、神に徹底的に拠り頼む信仰です。
【祈り】主よ、私は貧しく乏しいものです。あなたの助けなしには、与えられた生涯を真の意味で生きることはできません。いつでも、あなたの恵みとまことに信頼させてください。