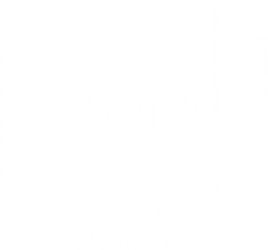先週土曜日9月27日午後に自民党総裁として高市早苗氏が選ばれました。政治家を一面的に見すぎたり、また一方的に批判することは、注意が必要であると申し上げた通りです。神のご支配の中で、権力者が立てられているという面もあります。(もちろん、明らかに神のみ旨に反する権力者もいますが……)
少なくとも株式市場は週明けの月曜日に4.8%もの記録的な上昇で彼女の就任を歓迎しました。これは石破首相が一年前に高市氏を破った翌日に、4.8%もの下落を示したことと好対照になっています。
高市さんは自分の理想とする政治指導者として1979年から1990年まで英国の首相を務めたマーガレット・サッチャー氏の名を上げています。ただ、サッチャーさんの政策は、アベノミックスとは異なる面があります。彼女は当然、そのことをよくご存じかと思います。
以下は12年前に小生が「お金と信仰」で書いたサッチャーさんの経済政策です
1929年の世界大恐慌からの脱出において、ケインズの積極財政政策が注目を集めました。現在の安倍政権も、基本的にその発想に従い、権力を行使した積極的な経済政策によって20年間のデフレ経済から脱却しようとしています。しかし、当時、世界大恐慌からどの国よりも劇的にすばやく立ち直ったのはヒットラー政権のもとでのドイツでした。それを目の当たりにしたオーストリアの経済学者フリードリッヒ・ハイエクは、政府主導の経済運営を批判して『隷属への道』という書を第二次世界大戦末期に著しました。
そこで彼は、市場経済における自由競争を制限しようとする多くの試みが、個人の勤労意欲やリスク管理能力、技術革新への情熱を減退させる方向に働いて長期的に経済活力を失わせること、またその矛盾をさらに政府が解決しようとして、ますます経済統制を強めざるを得なくなり、結果的に個人を国家に隷属させる方向に働くと警告しました(日本の農業の問題は、ハイエクの警告通りのことが起きた結果です)。
特に、戦後の英国経済などでは、社会的弱者の保護の美名のもとに国営企業の数が増え、政治家や労働組合の力が強くなり、自由競争が阻害され、慢性的な不況に陥って行きました。
そのような中でマーガレット・サッチャー氏が1979年に英国の首相の座に着きます。彼女は、学生時代にハイエクの『隷属への道』を読んで深い感銘を受けていました。そして保守党党首に就任してすぐに、ハイエクの『自由の条件』という書をテーブルに置き、「これがわれわれの信念です!」と叫んだとのことです。
彼女の政策に関しては様々な批判もありますが、英国病と言われた慢性的な経済の衰退から英国を脱出させた功績は、誰もが認めざるを得ないのではないでしょうか。
現在の安倍政権は、インフレ・ターゲット政策という壮大な実験を行っています。これは国債価格の暴落という悲劇を招く懸念もありますが、これが成功したとしても、将来への不安を残します。なぜなら、政府による経済介入の強化で実現した経済成長は、さらなる政治権力の肥大化を招く恐れがあるからです。規制緩和や民間活力の推進が看板倒れにならないことを祈るばかりです。
ハイエク氏の書に、「国家をこの世における地獄と絶えずしてきたのは、人々が国家をこの世における天国にしようとしてきた、あの努力以外のなにものでもない」という、驚くべき逆説が記されています。本当に、共産主義の提唱者たち、また、革命運動に身を投じた人々は、純粋な人々がほとんどでした。
でも、その純粋さが、人々を盲目にしたとも言えましょう。スターリン支配下のソ連や文化大革命時下の中国、ポルポト支配下のカンボジア、現在の北朝鮮、そこで起こった悲劇が明らかにされるなら、それはヒットラーのユダヤ人虐殺に匹敵するものとして、人々を驚愕させることでしょう。しかし、それを始めた人は善意に満ちていました。
また、ハイエクはその関連で、「ほんのしばらくの安全を手に入れるために、本質的で不可欠な自由を放棄してしまう人々は、自由も安全も持つ資格がない」ということばを引用しつつ、「自由とは代償なしには手に入れられないものである」と冷徹に記しています。
自由には恐ろしい過ちを生み出す力もありますが、それ以上に、何よりも過ちを正す力があります。しかし、安全を保障するはずの権力は、何よりも、自由から生まれる批判を封じる習性を持っています。ですから、権力によって経済を管理することには、後戻りできない破滅への道があるのです。
もちろん、市場経済の中で貧富の格差が広がり、人々の心が荒んでくるという危険もあります。しかし、経済に政治が関与し過ぎることにも、個人の主体性や自由を制限するというより大きな危険、「隷属への道」の危険性がるということを決して忘れてはなりません。
日本人は、あまりにも多くの事を政府に期待し過ぎるのではないでしょうか。それは政治権力をますます強くしてしまうことに他なりません。NPO法人のような非営利組織の活動に、もっと多くの活動の場を与え、私たちもそれを応援すべきではないでしょうか。
イエスの福音の核心は、何よりも「神の国」という概念にあります。それは、神のシャローム(平和、平安、繁栄)がこの世界を満たすことでした。預言者イザヤは「良い知らせ」の内容を、「あなたの神が王となる」(52・7) と表現しましたが、神はご自身の「王」としての権威を、人々を服従させる力によってではなく、「私たちの病を負い、私たちの痛みをになった」(同53・4) という苦難のしもべを通して現してくださいました。
私たちもまた、互いに仕え合うという生き方によって、この地に神の平和を広げるように召されています。権力に期待し過ぎることは福音の本質に反するのです。
歴史を振り返ると、社会の矛盾が増し加わるたびに、人々は独裁権力による解決を待望してきました。しかしそれは、「隷属への道」になりかねません。個人の主体性や自由を最大限に尊重しながら社会的な公正を目指すには、あらゆる常識を超えた神の知恵が必要なのです。
詩篇87篇1–7節「この者もあの者も この都で生まれた」
先の詩では、「すべての国々」がイスラエルの神を礼拝しに来ると記されていました (86:9) が、この詩では、エルサレム神殿の立つシオンの山が、全世界の祝福の「泉」となると歌われます (7節)。これは、歴史が「エデンの園」から始まって、「聖なる都、新しいエルサレムが……天から降って来る」(黙示21:2) ことで完成することを示します。
最初に、「主の礎は聖なる山にある。主 (ヤハウェ) はシオンの門を愛される」(1、2節) と記されますが、これは歴史的に、エルサレム神殿がバビロン帝国によって滅ぼされ、その後、バビロンを滅ぼしたペルシャ帝国の理解によって、神殿が再建されるという希望の中で歌われたと考えられます。
ただ、その第二神殿には、肝心の「契約の箱」も、主の栄光もありませんでした。それに対し、イエスがご自身の十字架と復活で、この神殿を完成すると語っておられました (ヨハネ2:19)。
現代の目に見えるエルサレムは民族的な争いの象徴の町とも見られがちですが、人間的には、和解が絶望的に見えるところにこそ、神の人知を超えた解決を期待することができます。ただ、それは政治的な意味での互いの譲歩による和解ではなく、真の和解をもたらす神のみわざを期待することです。
4節にはイスラエルの敵となった国々の名が記されます。ラハブとはエジプトの別の呼び名、バビロンはエルサレムを滅びした国ですが、これらがシオンを「知る者」、つまり、シオンを愛する者として記憶されるというのです。
またペリシテはイスラエルの仇敵、ツロはイスラエルの北にある地中海貿易で栄えた豊かな自由都市、クシュはエジプトの南のエチオピアを指す場合もありますが、当時は世界の南の端と思われていました。
これらの多彩な国々の民が、「この者は この都で生まれた」と呼ばれるようになるというのです。それは、「いと高き方ご自身が シオンを堅く建てられる」ので、「この者もあの者もこの都で生まれた」と言われ、主ご自身がこれらの異邦人の民を、シオンで生まれた民として登録されるからです。
イエスは「人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません」(ヨハネ3:3) と言われました。日本語を読み書きしてイエスを救い主と信じる私たちも、今、シオンで生まれた者として、神によって登録されています。
使徒パウロは、新約時代の「奥義(ミステリー)」として、「キリスト・イエスにあって、異邦人も共同の相続人になり、ともに同じからだに連なって、ともに約束にあずかる者になる」(エペソ3:6) と記しています。
それは当時の常識を覆すような「奥義」でした。当時は、異邦人が「神の民」となるためには、割礼を受け、食物律法等の様々な規定を守り、まずユダヤ人として受け入れられる必要があると思われていました。
しかし、パウロは、異端者扱いされながら、「異邦人はイエスを主と告白することだけで神の民とされる」と主張し続けたのです。しかし、それはこの詩にも記されているように、神がアブラハムを世界中の民の祝福の源として選んだときからの神のご計画でした。
キリストは、ユダヤ人と異邦人の間の「隔ての壁……を打ち壊し」「敵意を十字架によって滅ぼされました」(エペソ2:15、16)。それは世界中のすべての民族の和解につながることです。世界に民族間、宗教間の争いがありますが、「キリストこそ私たちの平和です」(同2:14)。
【祈り】主よ、エルサレムが今も、民族や宗教の争いの象徴と見られている現実に、心が痛みます。そのような中で、政治的な解決を議論する前に、キリストの十字架から生まれる真の和解を期待させてください。