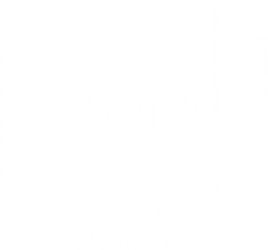最近、友人の勧めで米国の政治学者パトリク・デニーンの「リベラリズムはなぜ失敗したのか」という本を読みました。米国では右派からも左派からも高い評価を受けいている主張かと思います。
私たち福音自由教会は、個々人の良心の自由を何よりも尊重してきました。信仰や政治的な立場では、保守的と見られますが、実は「自由教会」という概念もとってもリベラル(自由主義的)なものです。
そこでは個人の自主、自律的な発想が尊重されます。それは民主主義の根幹をなす原理とも思われます。しかし、それは個々人の孤立を招く考え方にもつながるというのです。簡単に言うと、自分の意見を持ち、それを主張できる人は社会的な尊敬を集めることができることの罠です。
その反対にそれで自分の交わりを築くことができない人は社会で孤立し、居場所を失います。社会的弱者にやさしいはずのリベラリズムが、実は、それまでの伝統的な価値観を覆し、人々を孤独と不安に追いやってしまうというのです。
以前、霊性の神学の第一人者として尊敬されているジェームス・フーストン教授の「キリストのうちにある生活ー日本と欧米の対話の向こうに」の翻訳監修の働きをしたとき、そこで引用されていたチャールズ・テイラーという最近の哲学者のことを調べる必要がありました。脚注を書く際に次のような解説を僕自身の見解として書かせていただきました。
テイラーは A secular Age の中で、今から五百年前の宗教改革前の中世ヨーロッパの人々は、神を信じないという選択肢は、ほとんど考えられなかった。それは、魔法的な未知の不安に圧倒されていたとも解釈できる。
人々を魔法から目覚めさせたのは、科学の発展や機械文明などの「世俗」的な力であるが、それが皮肉にも人間の生きる意味などの別の根源的な不安や憂鬱を生み出したと説明している。
僕自身は中学生の頃から自分の生まれ育った村を恥じるように、自主自立の道を歩んできました。信仰に導かれても、いつも、伝統的な教会の権威的な教えに反抗するばかりか、自由教会の中でもそこにある権威的な教えに反抗しながら、自分の確信を大切にして来た面があります。しかしそこで様々な衝突やそこから生まれる不安を体験してきました。幸い今の僕には、多くの仲間や、僕が聖書から教えられたことを喜んで聞いてくださる応援者がいます。
しかし、そのようにできずに孤立していった多くの人々がいることも分かります。実はリベラリズムはそのように自主自律の道を開くことができる人と、そうはできない人の猛烈な格差を生み出す考え方なのかもしれません。
パトリック・デニーンはその中で、「ポスト・リベラリズム(自由主義以降)」という発想を勧めます。私たちは、伝統がすべてという魔法の時代に戻ることはできません。しかし、魔法の時代に存在した安心感のようなものを軽蔑してはならないのかと思います。
フーストン先生は日本人クリスチャンに、日本文化の中にある美しいものに目を開くようにと勧めています。僕も72歳になって改めて、日本文化の価値の再発見、また日本的な伝統を生かす人と人との関係づくりに目を向ける必要を感じています。
今回、ヨーロッパに住む多くの日本人を訪ねながら、「日本人らしさ」のようなものをヨーロッパと文化との対比で体験して来ようかと思っています。
今日は詩篇94篇の紹介です。とってもとっても乱暴な祈りが満ちていますが、そこには神のうちにある共同体への憧れがあるように思います。
詩篇94篇1–15節「復讐の神よ……報復を」
私たちは「復讐の神 主 (ヤハウェ) よ」という書き出しに戸惑いますが、これは先の93篇のテーマと同様に神の公平なご支配を歌った、苦難の中にある神の民にとって極めて現実的な祈りでした。
「復讐の神よ 光を放ってください 地をさばく方よ 立ち上がってください。高ぶる者に 報復してください」という祈りは、不当な苦しみを受けている者にとって、極めて自然な訴えです。「報復する」とは、「埋め合わせる」という意味で、自分ばかりがひどい目に合って損をしていることに対し、平等な状態になることを求める気持ちです。
ただし、これは自分で復讐や報復をするのではなく、神のさばきにゆだねる祈りです。それは、主ご自身が「復讐と報復はわたしのもの」(申命記32:35) と言っておられるからです。
使徒パウロは、このことばを引用しながら、「自分で復讐してはいけません」と述べつつ「神の怒りにゆだねなさい」と続けます。これは厳密には「御怒りに場所を空ける」という意味で、自分の怒りではなく、神の怒りが下されることで、神の正義が実現することへの期待です。
イエスは確かに、「自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい」(マタイ5:44) と私たちに命じておられますが、それは自分の敵に対する神の復讐の恐ろしさを知った結果の祈りとも言えます。敵のために祈ることができないのは、神が公平なさばきを実現してくださることを信じていない結果とも言えましょう。
「主 (ヤハウェ) よ いつまでですか 悪しき者が……勝ち誇るのは」(3節) という訴えは、私たちが不当な苦しみを受け続けたときに自然に湧きあがる気持ちではないでしょうか。そして、正直な気持ちを訴えられることこそ、神との対話の始まりです。
そればかりか著者は、自分の身近なところにいる社会的弱者が踏みにじられていることに心を痛めています。そして、「不法を行う者」が、「主は見ることはない。ヤコブの神は気づかない」と言い放っていることに憤りを覚えています。
それで、「気づけ。民のうちのまぬけな者どもよ」と呼びかけつつ、私たちの耳や目の創造主がすべてを「聞き」また「見て」おられることを思い起こさせようとしています (8、9節)。
また、「人に知識を教えるその方が……人の思い計ることがいかに空しいかを 知っておられる」(10、11節) とは、自分の知恵で神のご支配を否定することの愚かさを記したものです。
それを前提に、12、13節では、「なんと幸いなことでしょう。主 (ヤハウェ) よ あなたに戒められ……みおしえ(トーラー)を教えられる人は。わざわいの日に あなたはその人に平安を与えられます」と告白されます。それは「わざわい」が一時的なものにすぎず、そこに主の訓練と愛に満ちたご計画を見ることができる「平安」が生まれるからです。
そして、「悪しき者」に対する死のさばきと、主の民に対する永遠の守りが約束された上で、「こうして さばきは再び義に戻り」と告白されます (13–15節)。それは、神の公平なさばきが見えなかった状況が正されるという意味です。
また「心の直ぐな人はみな これに従います」とあるのは、誠実さが報われるという確信が生まれるからです。
【祈り】「復讐の神よ 高ぶる者に報復してください」と祈ることができる幸いを感謝します。あなたは「正直者がバカを見る」という不条理を放置なさらない公平な神であられます。いつでもどこでも、主のご支配の現実性を心に留めさせてください。