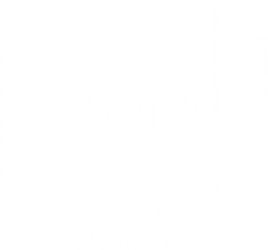世の中にはどちらの解釈も成り立つ小さな問題に固執して、その違いを大きく見せて対立を煽る人がいます。実はこの私にもそのような傾向があります。僕は最初、東京武蔵野福音自由教会の立川会堂の責任者として牧師の働きを始めましたが、初代牧師の古山先生が天に召され、英語部の牧師も東村山会堂の責任者もいなくなり、四つの礼拝の場を一人で責任を担う必要が一時的に生まれました。
そしてそのようなときに限って、いろんな問題が起きるばかりか、また僕自身も意見の対立を煽ってしまうようなところがありました。そのような中で「これほど必死に頑張っているのに、誰も僕の気持ちを分かってくれない」という深い孤独感に苛まれました。
そのとき慰めになったのが、「イエスは私の喜び」という古典的な讃美歌をアレンジしたJ.S. バッハの です。Mot とはフランス語で言葉を意味しますが、聖書のことばを無伴奏の多声部合唱で歌われます。バッハはローマ人への手紙8章1–11節と三十年戦争直後の混乱の中で生まれた讃美歌を絶妙に組み合わせました。
三十年戦争ではドイツの人口が場所によっては三分の一にまで減ったという信仰に名を借りた戦争ですが、それが1648年に終わった五年後の1653年に「イエスは私の喜び」という讃美歌が生まれました。
J.S. バッハは1723年にその六番までの讃美歌の間に、ローマ人への手紙8章1、2、9、10、11節の五つの節のみことばを解釈した声楽曲をはさみモテットとしましたが、これほど私たちに与えられた救いのすばらしさを確信させる曲はないとも思えるほどの曲です。これこそ最高の聖霊論の歌とも言えます。
目に見える状況は真っ暗闇なのですが、讃美歌作者のヨハン・フランクの心の眼は天のイエスに一心に向けられています。僕は大変だった時期、いつも目に見える結果に心を奪われていました。しかしこの讃美歌を聞いているとき、自分の心の動機が問われました。大切なのは何かの結果を出すことではなく、今ここでイエスの眼差しを意識しながら、イエスへの愛の行為としてすべてを行うということだと、改めて示されました。
不安な気持ちを抱えながら、今ここで、イエスとの交わり自体に喜びを発見できるのだと分かりました。この最初の歌詞(逐語訳)は、「イエスは私の喜び、私の心の牧場、イエスは私の誉れ(宝)。ああ、何と長く、ああ長い間、不安な気持ちの中で、あなたを慕い求めてきたことか。神の子羊、私の花婿よ。あなたにまさってこの地でこれほど慕わしい存在は私に何もありません」と歌われています。
私たちは様々な課題をこなすことで心が一杯になり、イエスの救いを遠く感じること、また自分の救いを疑うようなことがあるかもしれません。しかし、私たちはこの曲でイエスの救いを、今ここで体験できます。
1.「今や、決して処罰はありません、キリスト・イエスのうちにある者は」
7章14、15節でパウロは一人のイスラエル人として、「私たちは律法が霊的であることを知っています。しかし、この私は肉の者です。罪によって売り渡されています。自分のしている(生み出している)ことが私には分かりません。それは、自分が望むことを私が実行しているのではないからです。かえって、自分が憎んでいることを行っています」と自分の状態を描き、「なんとみじめな人間なのでしょう、この私は。だれがこの死のからだから私を救い出してくれるのでしょう」(7:24) と告白しています。
ただ、この嘆きの直後に、「しかし、神に感謝します、私たちの主イエス・キリストをとおして。こうしてこの私は、心では神の律法に仕えています。ただ肉では、罪の律法に仕えているのです」(7:25) と記しています。
それを受けて8章では、「こういうわけで、今や、決して処罰はありません、キリスト・イエスのうちにある者には」と記されます。
新改訳で「罪に定められる」と訳されていることばは、3節終りの「神はご自分の御子の……肉のうちにあって罪を処罰された」と記される「処罰する」の名詞形です。つまり、「すでに処罰が終わったので、処罰はない」と言われているのです。
多くの英語訳では There is no condemnation と訳されています。つまり、自分が「望むことを実行できずに、憎んでいることを行っている」という「みじめ」な状態を告白して、それで自己嫌悪に陥るのではなく、かえって「処罰はない」と宣言されるのです。
これは分かりやすい表現では、「もう地獄行きを心配する必要は全くない」という意味になります。
しかも、この「今や」ということばは3章21–24節で「しかし今や、律法から離れて、神の義が現わされたのです……すなわち、神の義がイエス・キリストの真実によって(を通して、媒介として)、すべての信じる人に与えられたのです……それはすべての人が罪を犯して、神の栄光を受けるに値しなくなっているからです。それで、神の恵みによって価なしに(無償で)義と認められることになりました、それはキリスト・イエスによる贖いをとおしてのものです」と記されていたことを思い起こさせる表現です。
とにかく、「なんとみじめな人間でしょう」と告白しながら、同時に、「キリスト・イエスにあって」、「今や、決して処罰はない(罪に定められることはない)」と言い切ることができるというのは何と素晴らしいことでしょう。
バッハはこの1節のことばを次のような歌詞として歌わせています。「こういうわけで、今や決してありません、決して処罰はありません、キリスト・イエスのうちにある者には。 その人は、肉に従ってではなく、御霊によって歩んでいます」
二番目の文章は当時の写本にあったことばで、本来、すべてのクリスチャンに当てはまるべきことばです。
ドイツ語の歌では「今や決してありません。決して処罰はありません」ということばが印象的に歌われています。しかも、その対象とされる人々は「キリスト・イエスのうちにある者」と描かれます。
確かにそれはキリストの真実を「信じる人」なのですが、「イエスのうちにある」とは私たちの信仰以前にイエスご自身から始まっていることです。
私たちの信仰は、神の聖霊のみわざによって始まったものです。イエスの十字架を自分の罪のためであったと信じる人に、何の処罰の恐れもないのです。
それをもとにこの讃美歌の二番目の歌詞が次のように歌われます。「御手のもとに やすらぐ身に 敵はなし たとい悪魔 力尽くし 脅すとも 罪と地獄が われを脅すとも 主はわが盾」
サタンの仕事は私たちにキリストにある救いを疑わせることです。そして、サタンは私たちに「おまえのような偽善者が、救われるはずはない。地獄こそがおまえの相応しい行き場所だと脅しますが、イエスこそがそのような攻撃から私たちを守ってくださいます。
キリストのうちに生きる者に対する「脅し」は何の力もありません。
二番目のみ言葉の合唱曲では2節の「それは、いのちを生む、いのちの御霊の律法(トーラー)が、キリスト・イエスのうちにあって、あなたを罪と死の律法(トーラー)から解放したからです。まさに解放したのです」と歌われます。
そこでは、「解放したのです」ということばが何度も歌われます。7章23、25節で繰り返された「罪の律法」ということばが、ここでは「罪と死の律法」と記されます。これは「聖なる神のみ教え(律法)」を守ることができなくて、自分は「死」に定められていると絶望する状態からの「解放」です。
これは5章20、21節で「律法が入ってきたことによって、違反が増し加わりました。しかし、罪の増し加わるところに、恵みも満ち溢れました。それは、ちょうど罪が死において支配したのと同じように、恵みもまた義(契約の真実)を通して支配するためでした。それは永遠のいのちのためで、私たちの主イエス・キリストをとおしてのことでした」と記されていたことを思い起こさせます。
私たちは今「いのちの御霊の律法」によって「罪と死の律法」から「解放」されているのです。すべては「いのち」を生み出す聖霊の働きです。
また7章では「私 (エゴー)」の悲惨さが描かれていましたが、ここではそれに対応するように単数形で「あなたを……解放した」と記され、しかも「いのちの御霊の律法」が、「罪と死の律法から解放した」と描かれます。
「律法」が「悪い」のではなく、アダムの「肉」を受け継ぐ者すべてに「罪が住んでいる」(7:17、20) ために、せっかく「善いもの」が「罪と死」を生み出したのです。
それで「いのち」を生み出す「御霊」が、「律法」を「いのちと死」の支配から、「キリスト・イエスのうちにあって」、「解放した」と言われるのです。
簡単に言うと、「神の律法 (トーラー)」を黙想しながら、それを実行できない自分に絶望する代わりに、神の御霊が自分に与えられ、それによって「永遠のいのち」が保障されていることをまず感謝することが出発点となります。
そこでは「律法」が努力目標ではなく、少しずつでも一つ一つ実行できたという感動を生みます。たとえばある人は、親のプレッシャーから逃げることばかりを考えていましたが、自分の人生を主にあって見なおし、証しを書いているうちに、両親への感謝の思いに満たされたと証ししておられます。「あなたの父と母を敬え……そうすれば、あなたは幸せになる」(エペソ6:2、3) が自分の体験となったのです。
2.「神はご自身の御子を罪の肉の似姿のうちに……遣わし……肉にあって罪を処罰された」
8章3–8節は、「それは肉をとおして弱くされ、律法には不可能になっていることに関して、神はご自身の御子を罪の肉の似姿のうちに、罪の(きよめの)ために、遣わし、肉のうちにあって罪を処罰されたからです。それは律法の要求(正しい判決)が満たされるためです、肉に従ってではなく御霊に従って歩む私たちのうちにです。
それは、肉に従う者たちのうちにあっては肉に属することを考え、御霊に従う者は御霊に属することを考えるからです。それは、肉の思い(考え)は死ですが、御霊の思い(考え)はいのちと平安だからです。なぜなら、肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に服従しません、いや、そうできないのです。肉のうちにある者は神を喜ばせることは、不可能です。」
つまり、私たちがどれほど心がけを変え、神に喜ばれる生き方を全うしたいと心を入れ替えても、「肉のうちにある」というアダムの生き方に倣う者は「神を喜ばせることが、不可能です」と断定されます。私たちはこの「不可能です」という宣言を、心の中で繰り返すべきでしょう。
これは単純に、どれほど良い行いをしたいという心がけを持っても、神を喜ばせることは無理ということです。まさに「地獄への道は善意(良い心がけ)で舗装されている (The road to hell is paved with good intentions)」と言われる通りです。
自分を神としたアダムに倣う「肉の思い」は「神に敵対する」ことを覚えるべきです。
ただ、ここで、「肉に従って歩む」代わりに、「御霊に従って歩む」とは、何か私たちが達成すべき目標かのように描かれているのでしょうか。
また、私たちの中では、「肉の思い」と「御霊の思い」がいつも格闘していて、私たちは自分の意思で「御霊の思い」を選び取らなればならないと勧められているのでしょうか。
しかしそれなら、再び、アダム以来の自分を神とした道に戻ってしまいそうです。そうではなく、すべての始まりは、この私のためになされた神のみわざを、感謝をもって受け止めることから始まります。それはたとえば、外を散歩しながら、目の前に咲いている美しい花を観賞することに似ているとも言えましょう。
その上で、讃美歌の三番目の歌詞では次のように歌われます。「悪しき力 たけり狂い 迫るとも われは立ちて こころ安く 主に歌う 神の御腕は 確かに伸ばされ われを包む」
ドイツ語では、Trotz(にも関わらず)ということばが繰り返されます。そこではサタンの攻撃が耐え難いように見えるにも関わらず、そのような恐怖のただ中で、そこに立ち続け、神の御手が力強く差し伸べられ、自分を包んでくださるということを体験できています。
サタンの攻撃はあり続けるのですが、そのただ中で神の守りの手を体験できるというのです。問題が消えることではなく、「心やすく 主に歌う」という告白こそが救いを現わします。
3.「キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなたがたの死ぬべき からだを生かす」
三番目のみことばの合唱は9節で、「しかし、あなたがたは肉のうちにではなく、御霊のうちにあります。神の御霊は、確かに、あなたがたの住んでおられます。だれかキリストの御霊を持っていないなら、その者は主のものではありません。キリストの御霊を持たないキリスト者はいないのですから」と歌われます。
そこではまず、「しかし、あなたがたは肉のうちにではなく、御霊のうちにあります」という断定形が強調されて歌われます。日本語訳では「神の御霊が……住んでおられると仮定したら」というニュアンスに受け取られるかもしれませんが、原文では、あなたがたはすでに肉のうちにではなく、御霊の支配に捕らえられ御霊のうちに存在しているという霊的事実を前提とした表現になっています。
これは6章11節で「自分は罪に対して死んだ者であり、神に対して生きている者だと、認めなさい(見做しなさい)」と命じられていたのと同じです。それはまた、「だれでもキリストのうちにあるなら、そこには新しい創造があります」(Ⅱコリント5:17) と宣言されるのと同じことです。
そして続く文章は、「神の御霊は、確かに、あなたがたの住んでおられます。だれかキリストの御霊を持っていないなら、それは主のものではありません」と訳せます。私たちは自分を「キリスト者(クリスチャン)」(使徒11:26) と定義づけますが、それは「キリストのもの」という意味です。
ここでは「キリストの御霊を持っていない」者が「キリストのもの」ではあり得ないと言われているのですから、聖霊またはキリストの御霊を受けていないキリスト者はあり得ないという意味になります。
それは「聖霊によるのでなければ、だれも『イエスは主です』と言うことはできません」(Ⅰコリント12:3)、また「人となって来られたイエス・キリストを告白する霊はみな、神からのものです」(Ⅰヨハネ4:2) と記されているように、ローマ帝国で十字架になった人を救い主と呼べる人間の中には「キリストの御霊」が「住んで」おり、その人は「御霊を持っている」のです。
ここでは敢えて「神の御霊」ではなく「キリストの御霊」と呼ばれ、すべてのクリスチャンが「キリストが私のうちに生きておられる」(ガラテヤ2:20) と言えることを指しています。
讃美歌の4番目では、「別れ告げよ 世の誉れや 世の栄え 主イエスこそは 永遠(とわ)に朽ちぬ わが誉れ 恥も悩みも われを主イエスより 引き離さじ」と歌われます。
肉のうちに生きる者は「世の誉れや 世の栄光」に心を奪われます。しかし私たちはすでに御霊のうちにあるのですから、その肉の誘惑にはきっぱりと別れを告げる必要があります。
私たちはキリストの御霊を持っているのですから、キリストのうちにある栄誉を味わい続けることができます。そのような中で、この世の多くの人々は「恥」や「悩み」を恐れてこの世的な平安を求めますが、いかなるものも私を主イエスより引き離すことはできません。
四番目のみことばの合唱では10節の「しかし、キリストがあなたがたのうちにおられるなら、からだが罪をとおして死んではいても、霊が義をとおしていのちとなっています。霊がいのちとなっています」と歌われます。
これも「キリストがあなたがたのうちにおられる」ことを「前提とするなら」という意味で、これは既に実現しています。ここでは私たちのうちにおられる「キリストの御霊」が「いのち」となっていると記されます。
これは5章21節の繰り返しでもあります。アダム以来の「罪」がこの肉体を「死」に追いやるのですが、「恵みが義を通して支配し」、それが「永遠のいのち」を生み出すというのです。キリストの御霊こそは「いのち」の源だからです。
そして、今回のモテット日本語訳バージョンでは、敢えて続く11節のことばの最初の部分を「今や、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊はあなたがたのうちに住んでおられるのです」として入れて、次の讃美歌につなげています。そうすることで全体の意味が明確になります。
この讃美歌の五番目の原文の歌詞では Gute Nacht(おやすみなさい)と繰り返しながら、この世の名誉や繫栄の誘惑と縁を切るように歌われています。
今回の翻訳では、その部分と続く11節のみことばの最初の部分をバッハの隠された意図を推測しながら挿入し、「永遠(とわ)に眠れ 世のいざない 世の力 イエスを死より 復活させた 主の御霊 わが内に住み 死ぬべきこの身も 生かしたもう」と歌います。
それは私たちが誘惑に勝つことができるのは、この世のすべてにまさる宝が私たちのうちに住んでくださっているからです。これは豪華なフランス料理をゆっくり味わう準備として空腹に耐えることに似ています。
五番目のみことばの合唱曲は11節をもとにしたもので、そこでは「今や、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊はあなたがたのうちに住んでおられるのです。それゆえ、キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなたがたの死ぬべき からだを生かすことになります、あなたがたのうちに住んでおられる御霊をとおして、あなたがたのうちに住んでおられる御霊をとおしてです」と歌われます。
原文の始まりは「しかし、もし、御霊が……住んでおられるなら」とも訳されますが、これは「そうであったら良いのに」という意味の仮定法ではなく、先と同じように現実に起こっていることを前提とした条件文です。たとえば荒野の誘惑で悪魔はイエスに、「もしあなたが神の子なら」と呼びかけましたが、これはイエスがご自身を「神の子」と宣言していることを前提とした表現です。
しかもここでは「イエスを死者の中からよみがえらせた方」の「御霊」と説明されています。これは父なる神がイエスを死者の中からよみがえらせたということを前提に、それと同じことが私たちに起こることを指しています。
Ⅰコリント15章20節で、「今や、キリストは眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました」と記されるように、キリストの復活は、私たちすべてがやがて「死者の中からよみがえる」ことの「初穂」なのです。
つまり、復活の御霊は確かに私たちのうちに「住んでいる」のです。しかもここでは「あなたがたの死ぬべきからだを生かす」と記されます。
私たちの身体は日々、死に向かっており、それが老化現象と言われますが、私たちのうちに住んでいる「御霊」は、そのような死に向かう身体を「生かす」というのです。
そのことを前提にパウロは、「たとえ、私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています」(Ⅱコリント4:16) と宣言しています。
「イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊」が、この私のうちに「住んで」いて、肉体的な死に向かっているこの「私」を、内側から生かし続け、「日々新たにしている」というのは何と感動的なことでしょう。
この霊的な真理が、自分に実現していることを思い起こし、それを日々感謝することこそが御霊に従う歩みです。そのような神の救いのみわざを思い起こさせる賛美を心から味わうことは何よりも有益です。
それを前提に讃美歌の六番目で、「去れ!悲しみ 喜びの主 イエス来ます 主を思えば 苦しみにも 安きあり わが苦しみを ともに担う主は わが喜び」と歌われます。
「去れ 悲しみ」とは厳密には「去れ、悲しみの霊」ですが、私たちが味わう「悲しみ」という感情を否定するという意味ではなく、今、「Freuden Meister」という「喜びの親方」が私たちの心の中に入って来るので、その方に「道を空けましょう」という訴えです。
悲しみの感情は大切なものですが、それに囚われすぎては自分も周りの人も不快にします。今、私たちのすべての苦しみを共に担ってくださるイエスがあなたの心の王座に就いてくださいます。私たちの人生には、「こんな苦しみはもうたくさん!」というものが訪れますが、今、ここでイエスがともにいてくださるなら、その苦しみのただ中で、この世の現実を超えた永遠の喜びを垣間見ることができます。
私たちの人生は「明日何が起こるか分からない」という不安の中に置かれています。それで多くの人は、下手な問題に首を突っ込まずに、自分の今のささやかな幸せを守り切ることばかりに目を向けます。
その中で、瀕死の重傷を負った同胞を見ても、見ぬふりをしてその前を通り過ぎるという善きサマリヤ人に登場する祭司やレビ人と同じ生き方をしてしまいます (ルカ10:30–32)。
しかしそのような生き方では、私たちの内側に「喜びの親方」(Freuden Meister) であるイエスをお迎えしていることの感動を体験することはできません。みこころであれば、苦しみのただ中でこそ、イエスは私の喜びと告白することができるのです。