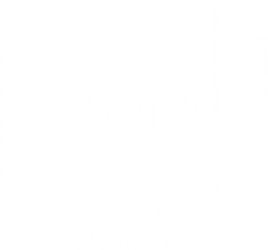レビ記は多くの人々から難解な書と思われ、しばしば敬遠されています。しかし、イエス・キリストの十字架の真の意味を、この書を飛び越えて理解することができるのでしょうか?
出エジプト記では、「雷鳴と稲妻と厚い雲」(19:10) とともに、主 (ヤハウェ) はシナイ山に降りて来られたと描かれました。そして、このレビ記では、その主が、人間と同じ地平まで降りた上で、会見の天幕からモーセに語りかけておられます。
太陽が近づきすぎると人々は焼き滅ぼされますが、今、全宇宙の創造主、全き聖である神が、汚れた民の真ん中に住んでくださるために、このレビ記の様々な規定が啓示されました。それこそ神の愛の表れです。
1.「主 (ヤハウェ) はモーセを呼び、会見の天幕から彼にこう告げられた」
レビ記の最初で「主 (ヤハウェ) はモーセを呼び、会見の天幕から彼にこう告げられた」と記されます。かつて神はモーセをシナイ山の上にまで呼び寄せましたが、今は、イスラエルの民と同じ地上にまで降りて来られ、彼らの真ん中に住み、そこから語ってくださったのです。
それこそが最高の奇跡でした。レビ記1~3章では「全焼のささげ物」「穀物のささげ物」「交わりのいけにえ」について述べられますが、ここではひたすら「祭壇の上で焼いて煙にする」ということばが繰り返されます (十回1:9、13、15、17、2:2、9、16、3:5、11、16)。
主へのいけにえは、人間の目には途方もない無駄と思えます。しかし、人間の愛は、何よりもそのような無駄を通して現されるのも事実ではないでしょうか。
しかしたとえば、しばしば妻たちの心は、夫が自分のためにどれだけお金や時間を犠牲にしてくれたかということによって動かされるのではないでしょうか。その反対に、自分の趣味や価値観を一方的に押し付けられることほど、不快なこともありません。
また「これは……主 (ヤハウェ) への食物のささげ物、芳ばしい香りである」という表現も七回繰り返されます (1:9、13、17、2:2、9、3:5、16)。新改訳第三版までは「主 (ヤハウェ) へのなだめのかおりの火によるささげ物」と記されていました。
その意味は、主 (ヤハウェ) ご自身が民の真ん中に住んでくださるための前提として、ご自身の怒りで彼らを「絶ち滅ぼしてしまわないように」(出エジ33:3)、「怒り」が「宥められる」必要があるということです。
それらのいけにえは、主ご自身が指定した方法でなければなりません。
これは、会社の金を使い込んで逃げた社員を再度迎えるかとか、浮気して逃げた伴侶を迎え入れるとかの手続きと似ているかも知れません。
罪を犯した人をそのままで受け入れたいと願っても、罪に対する明確な裁きがなされなければ罪を助長することになりますし、罪に対する「怒りが宥められ」なければ真の和解は成立し得ないからです。
なお「芳ばしい香り」は「安息のかおり」(英訳 NKJ では a sweet aroma、ESV では a pleasing aroma)とも訳すことができ、そこでは何よりも献げる者の心が問われています。
そのことが、詩篇50編8–14節では、主ご自身が、「いけにえのことで、あなたを責めるのではない。あなたの全焼のささげ物はいつもわたしの前にある……わたしが雄牛の肉を食べ、雄やぎの血を飲むだろうか」と皮肉を込めて言われながら、「感謝のいけにえを神にささげよ。あなたの誓いをいと高き神に果たせ」と、私たちの真心を求めておられます。
ここでは、いけにえをささげる者自身の動作に焦点が合わされています。まず、「主にささげ物をささげるときは、だれでも」(1:2)、野生ではなく自分で育てた「家畜の中から」最高のものを、会見の天幕の入り口まで自分で連れて来る必要があります。
そして「全焼のささげ物の頭に手を置く。それがその人のための宥めとなり、彼は受け入れられる」(1:4) と記されます。
これは以前「贖いとなる」と訳されましたが、「贖い」の本来の意味は、人を奴隷状態から解放することで、ここで問われているのは、献げた人が、神の前に受け入れられるための前提で、それが「ある人の怒りが宥められる」という場合と同じニュアンスで「宥め」と描かれます。これこそレビ記の鍵のことばです。
ですから、ここでは「全焼のささげ物」が「献げた」人のための「宥めとなる」ことで、その人が「受け入れられる」と記されています。手を置かれた家畜は、その人の罪を身代わりに負って血を流すのです。
しかも、携えてきた人自身が、家畜の叫びを聞きつつ「屠(ほふ)る」(1:5) 必要があります。
そして祭司は、流された血を受け取って「祭壇の回りに……注ぎかけ」ます。「血」は「いのちの象徴」ですから、これは、その人が「主 (ヤハウェ) の前に受け入れられる」(1:3) ことにつながります。
その上で、いけにえがすべて焼き尽くされ、煙となり「芳ばしい香り」となります。大洪水から救い出されたノアが「全焼のささげ物」を献げたとき「主 (ヤハウェ) は、その芳ばしい香りをかがれ」、「心の中で……『わたしは、決して再び人のゆえに、大地にのろいをもたらしはしない』」(創8:21) と言われました。
そこでは、主の怒りが、香りをかぐことによって宥められると考えられます。そこでは続けて「人の心が思い図ることは、幼いときから悪であるからだ」と記されながら、それにも関わらず二度と大洪水を起こしはしないと約束されているからです。そこから「生めよ、増えよ、地に満ちよ」(創9:1) という新たな祝福の時代が始まりました。
つまり、主の「燃える怒り」が「宥められる」とき、そこに恵みに満ちた主の「燃える愛」が明らかになったのです。ただそこでも、神はノア自身が払った犠牲の大きさに心を動かされたという面も見られます。彼は何しろ、箱舟で一年間余りの間、守り養い続けた動物をいけにえとしえささげてしまったのですから。
なお、いけにえは経済力に応じ、牛、羊またはやぎ、鳥と選ぶことができました。いけにえがその人にとっての最善のものである限り、それは「芳ばしい香り」として受け入れられるのです。
そして今の時代、神の御子ご自身が、私たちの身代わりのいけにえとなってくださいました。それは、「キリストも私たちを愛して、私たちのために、ご自分を神へのささげ物、またいけにえとし、芳ばしい香りを献げてくださいました」(エペソ5:2) と記されています。
そこではキリストの犠牲が「芳ばしい香り」と記されています。大洪水を起こした神の怒りが、ノアのささげものによって宥められたように、人の罪に対する神の怒りが、キリストの犠牲によって宥められるというのです。
ここでも、神がいけにえ自体を喜ぶというよりも、犠牲の高価さが強調されています。
なおローマ3章25節の「なだめの供え物」ということばは、言語学的には「宥めの蓋」と訳すのが正しいとも言われています。その前後は次のように訳すことができます。
「すべての人が罪を犯して、神の栄光を受けるに値しなくなっている……それで、神の恵みにより、値なしに義と認められることになりました。それはキリスト・イエスによる贖いを通してのものです。
神はこの方を『宥めの蓋 (mercy-seat)』として(公に)提示されました。真実を通しての、この方の血にあってのことです。それはご自身の義を証明するため……イエスの真実に基づく(イエスを信じる)者を義とするためでした」(3:23–26)。
「宥めの蓋」という場は、主がモーセに、また大贖罪の日に大祭司と会見し (レビ16:2)、ご自身のみこころを示す場でした。それは何よりも聖なる神が、罪人である私たちの真ん中に住んでくださることの象徴、またそこにおいて神がみことばを語ってくださるということの象徴でした。
そして今、イエスご自身が新しい「宥めの蓋」として私たちの真ん中に住み、父なる神を示し、新しい天と新しい地へと導いてくださいます。
神は、ご自身のひとり子の犠牲を、「芳ばしい香り」として受け入れられました。そして、そこに現されたキリストの真実を感謝して受け止め、その方に信頼して歩む者が、神の前に義と認められるのです。
神は、イエスがバプテスマを受けたときに、「あなたは、わたしの愛する子、わたしはあなたを喜ぶ」(ルカ3:22) と語りかけられましたが、その同じ語りかけが、イエスを救い主と信じるすべての人々に及んでいます。
2.「穀物のささげ物(神への貢物)」、「交わりのいけにえ(神との平和のささげ物)」
2章の「穀物のささげ物」とは、この世的には「貢物」を意味し、土地を与えられた臣民が領主の加護のもと外敵から守られ豊かな収穫を得られた見返りとして領主に持参したものでした。
これは「全焼のささげ物」に添えられたもので、「覚えの分(記念の部分)」(2:2) が「祭壇の上で焼いて煙に」された残りは、祭司たちの食物とされました。彼らは幕屋の奉仕に専念し、収入の道がないからです。これは、現代の教会の献金と同じような意味を持っています。
それにしても「覚えの分」でさえ「主 (ヤハウェ) への食物のささげ物、芳ばしい香り」と呼ばれるのは驚きです。後にパウロがコリントの教会に、「あなたには、何か、人からもらわなかったものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜ、もらっていないかのように誇るのですか」(Ⅰコリント4:7) と書き送ったように、私たちの才能も、健康も、仕事も収入も、すべては神の賜物だからです。
パウロはピリピの教会から経済的支援を受けたとき「私は……あなたがたの贈り物を受け取って、満ち足りています。それは芳ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださるささげ物です」(ピリピ4:18) と記しています。
なおここでも、献げる人自身の動作が、「もしあなた……穀物のささげ物である場合には……それを粉々に砕いて、その上に油を注ぎなさい」(2:5、6) と命じられます。
イエスは最後の晩餐で、パンを裂きながら「これはわたしのからだです」と言われました (Ⅰコリント11:24)。そこには主がご自分のからだを「贈り物」として弟子たちのために与えるという意味がありました。穀物のささげ物にもキリストの犠牲が示唆されています。
3章の「交わりのいけにえ」の「交わり」は平和(シャローム)に由来する言葉です。それは献げた者自身が家族とともに、主の前でその肉を食べますが、ここでは脂肪を選び分けて焼いて煙にすることに焦点が当てられます。
その際、牛、羊、やぎの三種類に関し、「内臓をおおう脂肪と、内臓についている脂肪すべて、二つの腎臓と……肝臓の上の小葉」(3:4、9、10、14、15) だけを選んで、「全焼のささげ物に載せて、焼いて煙にする」(3:5) よう命じられます。
ここでも、いけにえを自分の手で連れてきて、その頭の上に手を置いて、自分の手で殺すばかりか、その動物を解体して、脂肪を選び分ける働きは献げる人自身に課せられます。
その作業が牛、羊、やぎそれぞれで同じように繰り返されて描かれます。ここに献げる人自身の痛みが示唆されます。
なお、牛のいけにえに関しては、脂肪を焼いて煙にすることが、今までと同じように「主 (ヤハウェ) への食物のささげ物、芳ばしい香り」(3:5) と記されますが、羊とやぎの場合は敢えて主への「食物(パン)」(3:11、16) と描かれます。これは脂肪の全焼のいけにえが、主への最高の贈り物になるということの強調でしょう。
その上で「脂肪はすべて主 (ヤハウェ) のものである……あなたがたは、いかなる脂肪も血も食べてはならない」(3:16、17) と言われます。ヘブル語の「脂肪」の同音異義語には「最高」という意味が、「腎臓」は感情、意思の座という意味があり、神のみこころに全身全霊をささげることの象徴だったと思われます。
私たちの罪の始まりは、「神のようになって善悪を知る者となる」(創3:5) ことでした。それは「何が良くて何が悪いかを決めるのは、創造主ではなく、私です」と宣言することでした。
神はそのような自己中心の罪に怒っておられ、それが宥められる必要があります。
聖母マリアが「どうぞ、あなたのおことばどおり、この身になりますように」(ルカ1:38) と自分の身を差し出したことで、創造主は人となることができました。同じようにあなたも神に向かって自分を差し出すことで、神はあなたを用いて想像を絶する偉大な働きをしてくださいます。
神を善悪の中心、絶対者とすることは、自分の幸福、楽しみ、欲望を第一としたい人間にとってはときに大変な苦痛となります。
ですから神は罪人に対して「神を恐れる」ことを、具体的な行動を通して指示する必要がありました。それこそが、「神のかたち」に創造された人が真に生かされる道だからです。
神の恵みの高価さを忘れてはなりません。昔聞いた話ですが、祖母と孫の二人暮らしの家でのことです。孫はお金を持ち出す癖がありました。心を痛めた祖母は「今度やったら、この焼け火箸でお前の手を焼くよ」と警告しました。
それを見てその孫は、震えて「二度としません!」と誓いました。しかしそれから間もなく、また盗んでしまいそれが発覚しました。
孫は必死に謝りましたが、祖母は黙って座ったまま焼け火箸を火鉢から取り上げました。孫が目をつぶっている中で肉が焼ける音がしました。祖母は何と、火箸を自分の手に押し付け、大やけどを負いながらイエスの十字架の話をしたのです。
神の御子の十字架は、罪の結果の「のろい」を神の御子が引き受け、罪人をそのまま赦し受け入れたいと迫っくる高価な犠牲の伴った愛です。その愛を無駄にしてはなりません。その愛に応答することが求められています。
なお、イエスが「永遠のいけにえ」となってくださったからには、私たちはもう自分が育てた動物をいけにえにする必要はありません。しかし、そこで求められていたのは、私たち自身の「こころ」であるということは昔も今もまったく同じです。
それでヘブル書の著者は現代の「いけにえ」を、「賛美のいけにえ、(すなわち)御名をたたえる唇の果実」と「善を行なうことと分かち合うこと(コイノニア)」と表現しました (13:15、16)。
3.「罪のきよめのささげ物」「代償(償い)のささげ物」
4章では、「いけにえの血」に指を浸し、振りかけ、角に塗り、注ぐなどと、血生臭いことばが繰り返されますが、その趣旨は「ほとんどすべてのものは血によってきよめられるのです、律法に従えばですが。血を注ぐことなしには、赦し(解放)は実現しません」(ヘブル9:22私訳) とまとめられます。
人は罪に汚れたままで、聖なる神の前に立てません。それで神との交わりを回復するための手続きが必要になります。
そして、「人が、主がしてはならないと命じたすべてのことから離れて、気づかずに罪に陥り、その一つでも行ってしまった……場合」(4:2) の「罪のきよめ」の手続きが述べられます。「気づかずに」とあるように「知らなかった」という言い訳は通じず、「すべてのこと」が問われます。
そして「誰が罪を犯したか」によって、四種の方法が述べられます。
第一は「油注がれた祭司」の場合で、最も高価な「傷のない若い雄牛」を連れて来て、罪の身代わりとするしるしとして雄牛の頭に手を置き、自分の手で殺すことが命じられます。しかもその「血」を、会見の天幕の中の聖所に持って入り、至聖所を仕切る「垂れ幕の前に向けてその血を七度振りまく」るばかりか、その前の「香の祭壇の角」にも塗ります。聖所に仕える身で罪を犯したため、聖所がきよめられる必要があります。
第二の「イスラエルの全会衆」(4:13) が罪を犯した場合の手続きはほとんど同じですが、ここでは「こうして祭司は彼らのために宥めを行う。そして彼らは赦される」(4:20) と記されます。
第三は「族長が罪に陥って」(4:22) という場合のいけにえは「雄やぎ」です。その血は、庭にある「全焼のささげ物の祭壇の四隅の角」に塗ります。彼は聖所に入れませんから、きよめられる必要のあるのは、宿営の中の庭です。ここでも「祭司は彼のために罪を除いて宥めを行う。そして彼は赦される」(4:26) と記されます。
第四の「民衆の一人」(4:27) の場合のいけにえは「傷のない雌やぎ」、または「子羊」という二種類から一つを選ぶことができます。そしてその血は、庭の祭壇の角に塗られます。
そして最後に「祭司は彼のために、陥っていた罪を除いて宥めを行う。そして彼は赦される」と繰り返されます。
「宥めを行う」のヘブル語はキッペルで、そこから「宥めの蓋(カポレット)」という言葉が派生します。そこでの課題はすべて、主の前で「責めを覚える」(4:3、13、22、27、5:2、3、4、5、17) 者が、どのように神との交わりを回復できるかです。
5章1節での「証言しなければのろわれるという声を聞きながら、それをしない場合」とは、意識的に「なすべきことをしない」という罪です。この場合は「その人は咎を負わなければならない」と記されます。
そして次に「彼には隠れ」ていてという過失の中で「何か汚れたものに触れ」(5:2)、「人間の汚れに触れ」(5:3)、「軽々しく口で誓った」(5:4) 際に「後になって責めを覚える場合」と三度繰り返されますが、これらは「自分の不注意を後で気づく」ことで、その場合は「自分が陥っていた罪を告白する」(5:5) ことが求められます。 ここのテーマは良心の呵責ではなく、神の命令を破ったかどうか自体が問われているということです。
そしてそこでは「陥っていた罪のために償いとして……子羊であれ、やぎであれ、雌一匹を主 (ヤハウェ) のもとに連れて行き、罪のきよめのささげ物とする」(5:6) ことが命じられます。
ただその際「羊を買う余裕がなければ」(5:7)、「山鳩二羽……さえも手に入れることができないのなら」(5:11) という貧しい人への配慮も見られ、僅かな小麦粉しか献げられない人も、同じ「赦し」を受ける道がありました。
そしてこれらの箇所でも「祭司は……宥めを行う」(5:6、10、13)「そして彼は赦される」(5:10、13) と繰り返されます。ここでは罪の重さではなく、どのような立場の人が、また、どのような経済力を持った人がということで区別されています。
その目的は、神の前に受け入れられるという「罪のきよめ」です。そのことが何よりも明確なのは、「汚れたものに触れた」(5:2) 場合の「罪のきよめ」が、「民衆の一人」(4:27) の場合と基本が同じになっていることです。
ただし、悪意による意図的な犯罪の場合には、赦しを受けることはできません。それは、「モーセの律法を拒否する者は、あわれみを受けることなく、二人または三人の証言に基づいて、死ぬことになります」(ヘブル10:28私訳) と記されている通りです。
私たちは「謝るなら、赦される」と、罪を軽く見過ぎてはいないでしょうか。神は、過失の罪にさえ厳密ないけにえを定められました。
イエスが中風の人に「子よ……あなたの罪は赦された」(マタイ9:2) と宣言された時、律法学者がそれを「神への冒涜」と受け止めたのは当然とも言えます。神の御子ご自身が「罪のきよめのささげ物」となる計画があったからこそ、そう言えたのでしょう。
5章14節の「主 (ヤハウェ) はモーセにこう告げられた」は、主題の転換点の表現で、ここから「代償のささげ物」のことが述べられます。
「人が信頼を裏切ることをしたとき、すなわち、主 (ヤハウェ) の聖なるものに関して気づかずに罪に陥ってしまった場合」(5:15) とは、規定のささげ物の不足を「償う」ことだと思われます。
そのことが「彼は確かに主の前に償いの責めを負っていた」(5:19) とまとめられています。
特に6章では、人の財産を侵害した場合の賠償が述べられ、現代に適用できる原則があります。それは「かすめた品……」の「元の物を償い、また、それに五分の一を加えなければならない」という原則です (6:4、5)。
つまり、同じ額を返しただけでは「償い」にならないということです。それは、被害者の気持ちへの慰めにもなります。
しかもその上で、「傷のない、代償として評価された雄羊一匹を……代償のささげ物として、祭司のところに連れて行く。祭司は主 (ヤハウェ) の前でその人のために宥めを行う。彼は、自分が行って責めを覚えるようになったどのことについても赦される」(6:7) と明確に記されます。
預言者イザヤは、救い主が「自分のいのちを代償のささげ物とする」(53:10) と預言していますが、私たちは創造主の前に、償いきれないほどの負債を負っています。私たちはイエスの十字架を覚えながら、主の祈りで、「私たちの負い目をお赦しください」(マタイ6:12) と祈るように教えられています。
私たちはそれを口で慣習的に告白するのではなく、イスラエルの民が負い目を赦されるために何をしなければならなかったかを思い起こす必要があります。
これらの箇所では「祭司は……宥めを行う。そして彼は赦される」と9回も繰り返されながら「赦し」の宣言が心の底に響くように記されます (4:20、26、31、35、5:10、13、16、18、6:7)。
これらの規定は、神が、赦しがたい人の罪や負い目を、なお赦したいと願い、そのための手続きを定めてくださったという意味があるのです。
神は、罪人たちの真ん中に住むために、彼らとの交わりの仕切りとなる「罪」を「赦す」ための方法を提示してくださいました。そこで何よりも大きな役割を担うのが、祭司の働きでした。
しかし、イスラエルの歴史では、祭司たち自身が誰よりも早く堕落しました。神は彼らに非常に重い責任を与えたのですが、彼らは自分たちの特権ばかりを主張するようになり、神と民との間をとりなすための「宥め」のみわざの意味の根本を忘れていました。
それで今度は、主ご自身が「とりなす者」を備えてくださいました。それが、主イエス・キリストです。主は、常に、ご自分の側から民に近づこうとしておられます。そこで大切なのは、私たちが謙虚に自分の罪を認め、主の救いのみわざに心を開くことです。
レビ記に、民との交わりを求める主 (ヤハウェ) の燃えるような熱い思いを読み取る必要があります。私たちも、「どうせみんな罪人だし……」と居直ってしまったり、また反対に、「こんな自分は教会に来る資格はない!」と絶望したりと、心が揺れることがないでしょうか?
そこに共通するのは、御子の十字架を過小評価していることです。創造主ご自身が犠牲となられたのですから、赦すことのできない罪はありません。神はご自身の圧倒的な聖さを見せながら、同時に、いつまでも罪から自由になれない私たちをみもとに招いておられます。
そして今、「私たちは、イエスの血によって大胆に(天にある本物)の聖所に入ることができます」(ヘブル10:19) と告白できるのです。