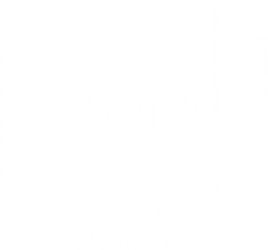私たちの心は、過去の痛みを忘れられるからこそ、ストレスを抱え続けないで生きて行けるのかもしれません。しかし、だからこそ、忘れてはならないことを覚え続けるため、記念の儀式が必要になります。
イスラエルの民にとって「過越の祭り」はその第一のもので、それは現在の教会では聖餐式として守られます。また、彼らがエジプト軍に追われながら分かれた海を渡ったことは、「バプテスマ」として記念されています。私たちの心が萎えてしまう時、神のみわざを思い起こすことは、心に希望を生み出します。
1.「主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた」
主(ヤハウェ)は、イスラエルを約束の地に導くにあたって「近道」を避け「荒野の道」へと遠回りさせました (13:17、18)。当時の通商ルートはエジプトの要塞で固められていたからです。
そして今、この不安の旅路を、「主 (ヤハウェ) は、昼は、途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は、彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた」(13:21) のでした。現代の私たちにも「昼は……雲の柱が、夜は……火の柱が、民の前から離れることはなかった」(13:22) ということはそのまま実現しています。それは聖霊が私たちのただ中に住んでくださっているからです。
パウロは後に、堕落したコリント教会に向かって、「あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らないのですか。もし、だれかが神の神殿をこわすなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなたがたがその神殿です」と述べました (Ⅰコリント3:16、17第三版)。
私たちがキリストのみからだである教会に集い、互いのために祈っているとき、私たちのただ中に創造主である聖霊ご自身が宿っておられます。私たちはこの教会から、それぞれの場に遣わされて行きます。そして私たちはこの交わりの中に生きることによって、主が「雲の柱、火の柱」によって、私たちの日々の生活を導いてくださっていることを体験することができるのです。
そこで不思議にも、主(ヤハウェ)はモーセに、「引き返して……海辺に宿営しなければならない」(14:2) と、逃げ道のない場に導きました。それはエジプトの王ファラオに、イスラエルの民が「あの地で迷っている」(14:3) と思わせ、彼らを追わせるように仕向けるためでした。
そしてファラオは精鋭の軍隊を引き連れて追跡しました。それを見たイスラエルはモーセに猛烈な皮肉を込めて「エジプトに墓がないからといって(王家の墓であるピラミッドを指した皮肉)、荒野で死なせるため、あなたはわれわれを連れて来たのか……エジプトに仕える(奴隷の)ほうがよかった」(14:11、12) と言いました。
しかしモーセは彼らに、「恐れてはならない。しっかり立って、今日あなたがたのために行なわれる主 (ヤハウェ) の救いを見なさい……主 (ヤハウェ) があなたがたのために戦われるのだ……あなたがたは、ただ黙っていなさい」(14:13、14) と答えます。
そして主(ヤハウェ)はモーセに、「イスラエルの子らに、前進するように言え……あなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けなさい……見よ。このわたしがエジプト人の心を頑なに(強く)する」(14:16、17) と言います。
この時、「雲の柱」はイスラエルの後ろに移動し、エジプト軍の追跡を遮りましたが、その情景が「雲と闇があって夜を照らした」(14:20協会共同訳) とも描かれます。これはイスラエルの前には光があったとも解釈できます。
そのような中で「モーセが手を海に向けて伸ばすと、主 (ヤハウェ) は一晩中、強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされた。水は分かれた」(14:21) というのです。これは真夜中のことで、強い東からの向かい風に逆らって、右と左が水の壁になっている海の中を渡るというのは大変です。彼らは背後にエジプト軍の恐怖があり、前には主の光があったからこそ、前進することができたのだと言えましょう。
私たちの人生にも「夜」の体験があります。しかし、エジプトの初子が打たれたのも、海が二つに分けられたのも夜でした。
詩篇77篇にあるように、夜に味わう不安と孤独は、「主 (ヤハウェ) の……不思議なみわざを思い起こし……恐ろしいさばきのみわざに、思いを巡らす」(11、12節私訳) きっかけに他なりません。昼の間は自分の力で忙しく動き回り、主を忘れがちだからこそ、主は、夜に救いをもたらされるとも言えましょう。
続けて「エジプト人は追跡し、ファラオの馬も戦車も騎兵もみな、イスラエルの子らの後を海の中に入って行った」(14:23) とは、自分から滅びに飛びこむ姿勢です。その後で、「主 (ヤハウェ) は火と雲の柱の中からエジプトの陣営を見おろし……陣営を混乱に陥れ、戦車の車輪を外してその動きを阻」みます (14:24、25)。
彼らはこの時になって初めて「イスラエルの前から逃げよう。主 (ヤハウェ) が彼らのために、エジプトと戦っているのだ」(14:25) と言いましたが、それは遅すぎました。そのとき主はモーセに、「あなたの手を海に向けて伸ばし、エジプト人と、その戦車、その騎兵の上に水が戻るようにせよ」(14:26) と言われます。
そして彼が再び「手を海に向けて伸ばすと、夜明けに海が元の状態に戻った……主 (ヤハウェ) はエジプト人を海のただ中に投げ込まれた……残った者は一人もいなかった」(14:27、28) と描かれます。
そして、これらのことが要約されるように、「イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を歩いて行った。水は彼らのために右も左も壁になっていた。こうして主 (ヤハウェ) は、その日、イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルは、エジプト人が海辺に死んでいるのを見た。イスラエルは、主 (ヤハウェ) がエジプトに行われた、この大いなる御力を見た。それで民は主 (ヤハウェ) を恐れ、主 (ヤハウェ) とそのしもべモーセを信じた」(14:29–31) と描かれます。
パウロはこれをもとに「私たちの父祖たちはみな(主の)雲の下にいて、みな海を通って行きました。そしてみな、雲の中と海の中で、モーセにつくバプテスマを受け」(Ⅰコリント10:1、2) と記します。つまり、この海を渡った記事は、私たちにとってのバプテスマを示しているのです。
イスラエルの民はこれ以降、エジプト軍の追撃を二度と恐れる必要はありませんでした。同じように私たちも既にサタンの支配から解放され、永遠のいのちを生きているのです。
そのことが「神は真実な方です。あなたがたを耐えられないような試練にあわせることはなさいません。むしろ、耐えられるように、試練とともに脱出の道を備えていてくださいます」(Ⅰコリント10:13) と記されます。あなたにとっての「神の真実」「脱出の道」は何を意味するでしょう。
この時、モーセとイスラエル人は「主に向かって歌い」、それが15章に記されます。現在の世界で起こっている様々な悲劇は、権力者たちが自分を神の代理とし、暴力を正当化することから始まります。
しかしここでモーセが行ったことは二回にわたって「手を海に向けて伸ばす」ことだけです。それに呼応するように、「主 (ヤハウェ) よ。あなたの右の手は力に輝き。主 (ヤハウェ) よ。あなたの右の手は敵を打ち砕く」(15:6) と歌われます。
そしてこれらすべての結果が「カナンの住民の心はみな溶け去った……主 (ヤハウェ) はとこしえまでも統べ治められる」(15:15c、18) と描かれます。つまり海が二つに分けられる奇跡を通して、最強の軍隊が主 (ヤハウェ) を恐れて戦いをやめ、近隣の国々もそれに倣ったのです。
人々が主(ヤハウェ)のご支配を認める時、この地に平和が実現します。主の「右の手」の力を信じられないからこそ、人々は武器を取って戦おうとするのです。私たちも、自分の力で問題を解決しようと動き出す前に、モーセに倣って、黙って手を差し伸べ、主に祈る必要があります。私たちに何よりも問われているのは祈りの手を上げることです。
ヘブル人への手紙では、神の御子が私たちと同じ「血と肉」を持つ身体となってくださった目的を、「それはご自分の死によって、死の力を持つ者、すなわち悪魔を無力化するためであり、また死の恐怖によって一生涯奴隷となっていた人々を解放するためでした」(2:14、15私訳) と記しています。
イエスの十字架は、サタンの勢力との戦の場だったのです。人間の目には、イエスが敗北したように見えましたが、罪のない神の御子が全人類のすべての罪を負って十字架にかかられたこと自体が、サタンに対する勝利宣言だったのです。
人はみな、「死の恐怖」につながれ、自分の身を守るために嘘をつき、人を裏切りますが、それこそがサタンへの敗北です。神はイスラエルを救うためにエジプトと戦われたように、イエスは十字架でサタンと戦い、復活によって勝利を宣言されました。それこそが十字架の神秘です。
2.「わたしは主 (ヤハウェ) 、あなたを癒す者だからである」
イスラエルの民はエジプトの戦車や騎兵の追撃から救い出されましたが、三日間、荒野を歩き (15:22)、ようやく見つかった水が「苦くて飲めなかった」とき、彼らはモーセに「われわれは何を飲んだら良いのか」と「不平を言った」と描かれます (15:24)。そこには困難を人の責任にする身勝手な思いがあります。
一方、モーセは「主 (ヤハウェ) に叫び」ました (15:25)。主は彼に「一本の木を示され……彼がそれを水の中に投げ込むと、水は甘くなった」と描かれます。
その上で「主はそこで彼に掟と定めを授け、そこで彼を試み」と記されます。これは、主が人の叫ぶのを待ち、不思議な解決を示し、それへの応答を見るという基本原則を授けたという意味だと思われます。モーセはこの試みによって、問題解決の原則を身につけたのです。
その原則が「もし……あなたの神、主 (ヤハウェ) の御声にあなたが確かに聞き従い(原文:聞いて聞く)、主の目にかなうことを行い、また、その命令に耳を傾け……るなら」(15:26)、「わたしがエジプトで下したような病気は何一つ……下さない」という約束です。
この結論としての「わたしは主 (ヤハウェ) 、あなたを癒す者だからである」という表現には、ご自身が人の叫びに耳を傾け、「苦い」苦しみを「甘い」喜びへと変えてくださるという響きがあります。
そのしるしが「エリム」という巨大なオアシスです。「十二の水の泉」と「七十本のなつめ椰子の木」という数字には、十二部族、七十人の長老 (24:1) などのように、すべてを満たすという意味があります。あなたの人生にも、困難を通しての「いやし」と、荒野の中でのオアシスが与えられます。
彼らは、エジプトの地を出て一か月が経過した「第二の月の十五日」、シナイ山北方320㎞ぐらいの地にある「シンの荒野」に入りましたが、そこで今度は食べ物のことで、モーセとアロンに「不平を言い」ます。
彼らは過去を美化し、「エジプトの地で、肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたときに、われわれは主 (ヤハウェ) の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実、あなたがたは、われわれをこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている」(16:3) と言いました。
彼らはエジプトで過酷な労働で苦しみ、主に叫び求めたのですが、それを忘れ、過去に一瞬だけ味わったことを異常に拡大して懐かしんでいます。残念ながら多くの人は、苦難に会うと、だれかのせいにすることでようやく精神のバランスを保とうとする傾向があります。
そして、そのとき非難の対象となるのは、それまで最も親身に世話し、援助の手を差し伸べた人です。日本の諺に「さわらぬ神に祟りなし」がありますが、関係を築いた結果として、謂れのない攻撃を受けるという現実があります。
しかし、そのような中で、「見て見ぬふりをする社会」という愛に渇いた世界を作りだします。パウロはコリント教会に向けて、「私があなたがたを愛すれば愛するほど、私はますます愛されなくなるのでしょうか」(Ⅱコリント12:15) と訴えましたが、残念ながら、それこそ愛することの報酬?と言えましょう。
しかし私たちはそこで、イエスの御跡に従っているという充実感を持つことができます。モーセ、イエス、パウロの歩みに共通するのは、助けることで恨まれるという理不尽です。
ところがそのような理不尽なイスラエルの民の不平に対し、主(ヤハウェ)は「天からパンを降らせる」(16:4) という解決を示してくださいました。
しかもその理由が「主 (ヤハウェ) に対する……不平を主が聞かれたから」(16:7、8、9、12) という趣旨のことばが四回も繰り返されます。主は彼らをさばく前に、不平を聞いてくださいました。その目的を主は、「わたしがあなたがたの神、主 (ヤハウェ) であることを知る」(16:12) ためと言われます。
また「夕方」には「うずらが飛んで来て、宿営をおおい」(16:13) ます。それは体長20㎝程度のきじ科の鳥で、高くは飛べないほど太っていますから、小さいわりに栄養になります。
その上、朝になると、宿営の回りに「薄く細かいもの、霜のような細かいもの」がありました (16:14)。それこそ天からのパン、蜜を入れた薄焼きパンのようなもので「マナ」と名づけられます (16:31)。
それを各自、自分たちが食べる分だけを集めましたが、不思議にも「たくさん集めた人にも余ることはなく、少しだけ集めた人にも足りないことはなかった」(16:18) と描かれます。
ところが、明日を心配し、自分の分だけを残して置く者がいました。しかしそれは朝になると虫がわき、悪臭を放ちました (16:20)。ここに自分のためだけに富を蓄える空しさが示唆されます。
一方で主は「六日目に……二倍のパン」を集めるように命じ (16:22)、七日目に休めるようにさせました。安息日の教えが描かれるのは創世記2章以後初めてで、六日目のパンは、翌朝まで保存しても「臭くもならず、うじ虫もわき」ませんでした (16:24)。
それでも民の中のある者は、七日目にも集めに出ました。しかし、何も見つかりません。ここに主のみこころに反した働き方が徒労に終わるという原則が見られます。
主は、七日目に休むことを命じられると共に、必要を満たして下さいます。「人はパンだけで生きるのではなく、人は主 (ヤハウェ) の御口から出るすべてのことばで生きる」(申命記8:3) とは、決してパンの必要を軽んじることではなく優先順位の問題です。主を第一として生きる結果、無駄な働きで身体を壊すことなく、全ての必要も満たされます。
主は、イスラエルの民の「不平」を優しく受け止めてくださいました。しかしそれは彼らを幼児として扱っているからに過ぎません。成長するにつれ、主は彼らに厳しく向き合うようになられます。
そこで必要なのは、神を非難する態度ではなく、主にへりくだって必要を訴えることです。
3.「主 (ヤハウェ) は私たちの中におられるのか、おられないのか」
17章ではイスラエルの民は今、「この山で神に仕える」(3:12) という目的地の麓の「レフィディム」にたどり着きましたが、「飲み水がなかった」(17:1) ので、「民はモーセと争い」(17:2) ます。
そこで彼らはまたも「モーセに不平を」「いったい、なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか。私や子どもたちや家畜を、渇きで死なせるためか」と言い、「石で打ち殺そう」(17:4) とさえしました。
彼らは、海がふたつに分かれて救い出されたこと、苦い水が甘い水に変えられたこと、巨大なオアシス、エリムでの休息、天からのパンの恵みなどのすべてを忘れたかのように、目の前の渇きに忍耐できずに怒るばかりです。
この情景は、イエスがローマ総督ピラトの前で無力な姿で立った時に、ユダヤ人たちが一斉に「十字架につけろ」と叫んだことに重なります。イエスも男だけで五千人の人々にパンを与え、多くの病人を癒し、当時のユダヤ人に徹底的に寄り添っておられました。
しかしイエスが彼らをローマ帝国の支配からの解放できないと分かったとき、彼らはイエスに死刑を要求しました。全体像を見られず、目の前の状況にパニックになる点では同じです。
しかし「モーセが主 (ヤハウェ) に叫ぶ」(17:4) と、主は「あなたがナイルを打ったあの杖を手に取り、そして行け……わたしはそこ、ホレブの岩の上で、あなたの前に立つ……その岩を打て。岩から水が出て、民はそれを飲む」(17:5、6) と言われます。
そして岩から水が湧き出たのですが、「それで、彼はその所をマサ(試み)、またメリバ(争い)と名づけた。それは、イスラエルの子らが争ったからであり、また彼らが、『主 (ヤハウェ) は私たちの中におられるのか、おられないのか』と言って、主 (ヤハウェ) を試みたからである」(17:7) と記されています。
彼らはそれまで、「雲の柱、火の柱」の導きとともに、様々な偉大なみわざを見ながらも、ここでは主のご臨在自体を疑ってしまいました。
彼らとしては、せっかく当面の目的地に着いたという思いがあり、そこは楽園とは正反対の不毛の地であったことに深く失望したのかもしれません。モーセは後に「あなたがたがマサで行ったように、あなたがたの神である主 (ヤハウェ) を試みてはならない」(申命記6:16) と警告します。
神は創造主として人を試み、人の成長をもたらされます。しかし人が神を試みるとは、神を自分の期待通りに動かそうとする傲慢さです。しかし神はここでも、民の忘恩をさばく前に、彼らの渇きを癒し、信仰を育んでくださいました。
この世では、一回の失敗で、それまでのすべての信頼関係が崩れるということがあります。しかし、真の信頼関係とは、目先のことが自分の期待外れであっても、それまでのすべての歩みを振り返りながら、今、ここでの不条理と思える状況を、忍耐を持って待つことができることなのです。
ところで、オアシスの占有権は遊牧民にとっての死活問題でした。アマレク人はシナイ半島の荒野を行き来している遊牧民ですが、レフィディムに豊かな泉が湧いたことを耳にし、それを奪おうと攻撃をしかけて来ました (17:8)。これは一つの民族とされた彼らにとっての最初の戦いです。
このときモーセはヨシュアを司令官として指名し、自分は「神の杖を手に持って、丘の頂に立ちます」(17:9)。実際の戦いでは「モーセが手を上げているときは、イスラエルが優勢になり、手を下すとアマレクが優勢になった」(17:11) のでした。
そしてアロンとフルが両側でモーセの手を日が沈むまで支えることで「ヨシュアは、アマレクとその民を剣の刃で打ち破った」(17:13) というのです。手を上げるとは、祈りの姿勢です。これは主(ヤハウェ)とアマレク人との戦いでしたので「主 (ヤハウェ) は代々にわたってアマレクと戦われる」(17:16) と言われます。
神は後に、サウルを用いて彼らを絶ち滅ぼされました (Ⅰサムエル15章)。私たちも、すべての戦いを、神のご支配と観点から見直すようにしなければなりません。すべての戦いは霊的な戦いであり、勝利の秘訣は祈りです。
イスラエルの民はエジプトへの十の災い、海が分けられ、天からマナが降り、岩から水が湧きだし、アマレクを打ち破るなどの圧倒的な主(ヤハウェ)のみわざを見ながら、目の前に苦難が訪れると、主に「不平」を言うばかりか、自分たちのただ中に「主 (ヤハウェ) がおられる」ことを忘れました。これほど頑なで、不信仰な民族がいるのかと思えるほどです。
しかし、彼らこそアダムの子孫である肉なる人間の見本です。本日の「みことばの光」の箇所のエレミヤ17章9節に「人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。だれがそれを知り尽くすことができるだろうか」と記されています。
「ねじ曲がっている」とは「欺くもの」とも訳され、イスラエルの始まりである「ヤコブ」と同じ語根のことばです。イスラエルは人の心の闇の深さを現わす見本とも言えますが、その民の子孫として救い主イエスが生まれ、その罪ばかりか全世界の罪を負って十字架にかかられたのです。
私たちも自分の罪や不信仰を示されて自己嫌悪に陥ることがありますが、イスラエルの不平と不信仰に耐えられた神は、あなたのためにもイエスを十字架にかけてくださいました。
私たちはみな、あまりにも近視眼的に、自分自身の置かれている状況からしか物事を見ることができずに、神の永遠の救いのご計画を忘れてしまいます。
深く反省して自分を変えられるぐらいなら、十字架も聖霊のみわざも必要ありません。自分や人に失望しても三位一体の創造主に失望してはなりません。イスラエルの不平に耐えて導かれた神は、あなたの心をも内側から造り変えることができるからです。