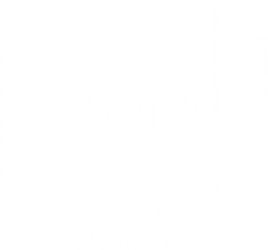先日10月21日、NHKのBS「新日本風土記」で僕の故郷の東川町の美しさが一時間にわたって放映されました(北海道旭川市の東にある田舎町)。
北海道の地方の町はどこも人口減少が激しいですが、東川町は過去20年あまり人口が増えて続けています。それでも8000人余りですが……
その第一の理由は、湧き水の美味しさにあると言われていました。大雪山の最高峰の旭岳 (2291m) は東川町の中にあります。その雪解け水が東川町のどこの地下からも湧き出ています。東川町は上水道の要らない町として全国的に有名です。自然のミネラル豊富な水からできるお米もその美味しさで注目されています。豆腐もコーヒーもおいしいです。
観光資源からの税収も多く、40年ほど前から多くの留学生を受け入れ、日本語教育を応援しています。僕の姉は留学生のための茶道教室のお手伝いをしています。NHKの番組で、何よりも東川に住む人はみんな優しいと報じられていたのが嬉しかったです(そんなに違うとは思いませんが、でも父母がお世話になった施設のスタッフは確かにみんな本当に優しかったです)。
全国的に注目される憧れの町が、僕の故郷だなんて、夢のような話です。
でも、小学校、中学校時代の僕は、自分の田舎を恥じていました。昔は自家用車などありません。歯医者の治療を受けるために親戚の家に泊めてもらう必要があったほどです。僕の幼児期に死を覚悟せざるを得ないほどの重病になったとき僕の母は片道3時間近くかかる旭川の市立病院まで、泣きながら駆けつけました。救急車もなかったからです。
中学生頃から学校の成績が上がり出した僕は、世界に羽ばたくビジネスマンになることに憧れました。その夢がかなってドイツで仕事をしながら、故郷の美しさに目が開かれて、毎年のように旭岳やその付近を登山、散策するようになりました。
つい最近まで僕の本籍は東川町にありましたが、父が大切にしていた水田も町の政策に合わせて売らざるを得なくなりました(驚くほどの安値)。
すると何と今回のNHKの報道では僕の家と昔の水田が映されました。写真甲子園に参加した高校生が、水田拡張工事で働く人の姿を映していましたが、何とその舞台が僕が数年前に売らざるを得なかった水田だったのです。神様の哀れみを感じました。
聖書の教えで何よりもユニークなのは安息日の教えです。その核心は、何よりも神から一方的に与えられている恵みを喜ぶことです。
それぞれが当たり前のように受けている恵みを、感謝することを忘れることから人間の絶え間ない競争が始まります。そこには永遠の喜びなどはありません。
詩篇92篇1–15節「御手のわざを喜び歌う」
ここには「安息日のための歌」という標題がついていますが、これはヘブル語詩篇の中で唯一のものです。
ユダヤ人の伝承の中では、「ユダヤ人が安息日を守ったというよりは、安息日がユダヤ人を守ってくれたのである」と言われます。第二次大戦後にイスラエルという国家と現代ヘブル語が突然誕生したのはこのためとも言えましょう。
なお安息日の教えは出エジプト記20章では、「主が六日間で世界を造り、七日目に休んだから」という天地創造に目が向けられますが、申命記5章では、イスラエルの民がエジプトでの奴隷状態から解放されたことを覚えて、奴隷を休ませるという面に目が向けられます。
イエスが、「安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために造られたのではありません」(マルコ2:27、28) と言われ、生まれつき目の見えない方や、足のなえた方を、敢えて安息日に癒されたのは、この日を解放の日として喜ぶためでした。
原文での冒頭のことばは、「良い(麗しい)ことです」という描写から始まりますが、それは1–3節全体を指してのことです。
神の目に何よりも「麗しい」ことは、「主 (ヤハウェ) に感謝」し、主の「御名をほめ歌う」こと、また主のご性質である「恵み(ヘセド:契約の愛)」と「真実(エメット)」を、「十弦の琴」や「竪琴の妙なる調べにのせて」歌いながら」、「朝に」また「夜ごとに」、「告げる」ことであるというのです。
その理由が4節で「私を喜ばせてくださいました」と描かれます。これは出エジプトの救いから始まるすべての主の働きが、私の喜びとなったという意味です。それがさらに、「あなたの御手のわざを 私は喜び歌います」と記されます。私たちは日々の生活の中で、何か自分や家族が達成した成果を喜び、誇りがちですが、主にとって最も「麗しい」ことは、様々な楽器を奏でながら、主ご自身のご性質を、また主のみわざを喜び歌うことなのです。
著者は引き続き5、6節で、主のみわざの「大きさ」や「御思い(構想:designs)」の不思議さを賛美しながら、「無思慮な者は知らず 愚か者には これが分かりません」と告白します。人はしばしば、目の前の課題や、仕事や人間関係ばかりに目が向かって、この世界が神の不思議で満ちていることを忘れてしまいがちだからです。
この社会では、「無思慮(鈍感)な者」である方が、傷つかずに済むかもしれませんが、それでは神と人との真の心の交わりは生まれません。この世的には知性が高いように見えても、すべてが当たり前ではないということに気づかない者は、「愚か者」に過ぎません。
8節はこの詩篇の中心点です。神は、この世界を超えた、はるかに高い「御座」からこの世界のすべてを支配しておられます。
私たちは、「神が全世界を治めておられるなら、なぜこのような異常気象や自然災害が起きるのか?」と思いがちですが、火山活動で生まれた日本列島の上で、日々を平穏のうちに暮らしていること自体が圧倒的な不思議とも言えます。ときおりの自然災害は、恵みの偉大さを思い起こす契機となります。
さらに、9節は先の7節に対応し、10、11節は4–6節に対応し、12–15節は1–3節に対応します。そして、主に感謝し、賛美する者が、神の目に「正しい者」と見られ、その人の人生が豊かに祝福されるようすが生き生きと描かれて行きます。
【祈り】主よ、私たちは毎日、何かに駆り立てられるように忙しく生きてしまいがちです。どうか、安息日の恵みを思い起こさせてください。主の天地創造のみわざ、また歴史に現わされた圧倒的な救いのみわざを思い起こし、感謝する者とさせてください。