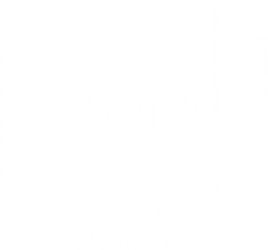この度、欧州を24日間旅して、改めて日本の住みやすさを実感しました。それは自分の常識的な感覚が通じるという安心感です。その背後に日本固有の神話的な物語が集合的無意識のように共有されているのかもしれません。
もっとも古い物語の古事記を読むとそれが見えて来ます。しかもそこには明らかに聖書の影響を見ることができます。日本の古典は聖書の福音の福音のすばらしさを際立たせます。
キリスト降誕から約七百年後に編纂された古事記には、天の神が地に下って王となるという発想以外にも、様々な聖書の影響が見られます。天皇という称号が生まれたのは7世紀後半であると言われますが、712年に編纂された古事記では、天皇の起源が記されます。
まず、アマテラス大神はイザナギが黄泉の汚れを清めるため阿波岐原で禊(みそぎ)をした際、左目を洗った際に生まれます。彼女は太陽神と称され、その孫のニニギノミコトが三種の神器を預かり、神々を従えて今の宮崎県に下ることが天孫降臨と呼ばれます。
その後ニニギノミコトは山の神の娘と結ばれ、そこから生まれた山幸彦は、海の神の娘と結ばれ、彼の四人の孫たちは日本列島の中心に向けて東征を開始しますが、兄たちそれぞれ消え去る中で末弟が大和の地(奈良県)に王宮を建てて瑞穂の国全土の支配者となり神武天皇と称することになります。
それに比べ、ヨハネ福音書の書き出しは驚くほど合理的でありながら奇想天外です。そこでは何と全宇宙の創造主が、歩くことも話すこともできないひ弱な赤ちゃんになったと記されています。
この世では、それぞれがより強く、より賢く、より豊かになろうと競い合っていますが、何でもできる方が何もできない赤ちゃんになったということを祝うのがクリスマスです。
ここには私たちの常識を逆転させるメッセージが込められているのです。使徒ヨハネは、クリスマスを「神が人となられた」ことを記念する日として描いています。
1.「ことばは人となって、私たちの間に住まわれた」
この福音書は、人となる前のキリストが「ことば」として表現され、「ことばは神であった」と大胆な宣言がなされます。それは、三つの観点から説明されています。
第一に、「この方は、初めに神とともにおられた」(2節) とあるようにキリストは世界が始まる前から御父の神とともにおられたということです。世界は神の愛の交わりから始まり、全被造物を含む愛の交わりで完成するのです。
第二は、「すべてのものは、この方によって造られた」(3節) ことです。キリストは人である前に、万物の創造主であられます。
第三は、「この方にいのちがあった。このいのちは……すべての人を照らしているまことの光」(4、9節) だったことです。「照らしている」とは、英語でenlighten(啓蒙する)とも訳した方が良いとも言われます。
つまり、主は、歴史の始まりから人の心を照らしておられ、また、どんな闇に満ちた心をも造り変えることができる方なのです。
そして、「この方」が世に来られることが三段階で描かれます。
第一は、「光はやみの中に輝いている」(5節) です。それゆえ主を知らない人でも、暗やみの中にも希望の光を見出すことが可能になります。
第二は、「まことの光が世に来ようとしている」(9節) です。神は預言者を通してご自身の計画を語り続けて来られましたが、今このときには、光の創造主ご自身が、暗い世界のただ中に降りてこられたというのです。
第三が「ことばは人(肉)となられた。そして私たちの間に住まわれた」(14節) で、これこそ想像を絶する奇跡です。
たとえば1秒間に地球を7回半回る光の速度で銀河系の端から端まで十万年かかりますが、宇宙にはそのような銀河が無数にあり、今分かっている限界まで光の速度で470億年かかります。太陽一つが地球に近づくだけですべてが蒸発するというのに、誰が全宇宙の創造主を見られるのでしょう。
その創造主が「人(肉)となった」というのです。「人」は原文で「肉」とも訳されることばです。それはあらゆる弱さを抱えた、朽ちて行く身体です。
それは、ご自身の栄光を肉体の中に隠すためであり、人が神の本質を知ることができるためです。私たちはイエスの弱さの中に、創造主としての「栄光」を見るのです。
なお、「私たちの間に住まわれた」(14節) で、「住む」とは「幕屋を張る」という原語が用いられます。主が、シナイ山に降りて来られた時、「煙は、かまどの煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた」(出エジ19:18) と描かれます。
その神が「わたしはイスラエルの子らのただ中に住み、彼らの神となる」(出エジ29:45) と言われたのです。
そして今、すべてを焼き尽くす力を持つ栄光の神は、「幕屋」ではなく、肉の姿となられたイエス・キリストによって、罪ある私たちのただ中に住み、真の自由と平和を実現してくださるのです。
これこそ、救いの本質です。多くの人々は、マリアが処女のままイエスを産んだという処女降誕をあり得ないことと否定します。しかし、それよりも何よりも、全宇宙の創造主が私たちと同じ人間になられたということ自体が何よりの不思議なのです。
神学的には、イエスの誕生は、「受肉」と呼ばれます。これは、神のことばが肉体を受けられたという意味です。永遠に生きる神が、死ぬべき肉の身体となったのです。
三世紀から四世紀にかけ、キリストが神であることを否定する誤った教えが広がりました。それに対して、正統的な信仰を守るために戦ったのがアタナシウスです。
彼の名は、一般の高校の教科書にも出てくるほど有名です。彼は「ことばの受肉」という日本語訳で80ページぐらいの文書を記しています。
その中で彼は、「ことばが人となられたのは、われわれを神とするためである」という有名な命題を記します。それは私たちが「欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質にあずかる者となる」(Ⅱペテロ1:4) という意味です。
人類の父アダムは、欲に負けて善悪の知識の木の実を取って食べ、滅びる者となりました。その後、「欲によって滅びる」という原理がすべての人を支配しています。事実、神が創造された美しい世界は、人間の欲望によって、救いがたいほどに腐敗してしまいました。
その原因は、神のかたちに創造された人間が、創造主である神から離れて生きるようになったためですが、人間の腐敗は、「教え」や「悔い改め」では癒しがたいほどに進んでしまいました。
それに心を痛められた神は、ご自身の御子をこの世界に遣わしてくださいました。御子は私たちの創造主であられますが、ご自身でこの腐敗してゆく肉体を持つ身体となることによって、腐敗する身体を不滅の身体へと変えようとしてくださいました。
すべてのいのちの源である方が、死と腐敗の力を滅ぼすために、敢えて、朽ちて行く身体を持つ人間となられたばかりか、最も惨めな十字架の死を自ら選ばれたというのです。
そのことを聖書は、「子たちがみな血と肉とを持っているので、イエスもまた同じように、これらのものをお持ちになりました。それはご自分の死によって、死の力を持つ者、すなわち悪魔を、無力化するためであり、また、死の恐怖によって一生涯奴隷となっていた人々を解放するためでした」(ヘブル2:14、15私訳) と記しています。
そのことの意味は、キリストの弟子たちに起こった変化によって知ることができます。ローマ帝国は、紀元三百年頃まで、クリスチャンを絶滅しようと必死でした。彼らは皇帝を神として拝む代わりにイエス・キリストを神としてあがめていたからです。ところが殉教者の血が流されるたびに、クリスチャンの数が爆発的に増えてしまったのです。それは、クリスチャンたちの死の脅しに屈しない姿が人々に感動を与えたからでした。そこには真のいのちの輝きが見られました。
それは弱さの中に現れる神の力です。そして最後の大迫害の後まもなく、ローマ帝国はイエスの前にひざまずきました。
ローマ帝国で皇帝の権威が平和の基と言われ、皇帝礼拝が強要されましたが、戦前の日本でも同じことが起きました。古事記を初めとする神話の核心には、天皇の存在こそが日本の平和と繁栄の基礎であるという趣旨が記されています。確かに国民主権を大切にする現在の日本国憲法においても「天皇は国民統合の象徴」と記されています。
しかし天から地に降りられた方の最初の住まいは、貧しく汚い「飼い葉桶」でした。しかも、主は今、ご自身の霊によって、貧しく汚れた私たちの身体に住んでくださいます。実は、聖書に記された救いとは、天地万物の創造主が私たち一人ひとりを天の神の子、つまり天皇のような存在にすることにあるのです。
それが今、可能になっています。なぜなら、私たち一人ひとりの身体のうちに創造主なる「キリストの霊」が既に宿っているからです。私たちの内に住んでおられる創造主ご自身のいのちが、周りの人にも明らかになるほど輝きを放つことができるのです。
ただそれは、周りの人々に恐れの気持ちを抱かせるような能力や人格的な輝きというより、弱さの中に現わされる復活の「イエスのいのち」(Ⅱコリント4:11) です。
その不思議をパウロは逆説的に「私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。
私たちは、いつもイエスの死を身に帯びています。それはまた、イエスのいのちが私たちの身に現れるためです。私たち生きている者は、イエスのために絶えず死に渡されています。それはまた、イエスのいのちが私たちの死ぬべき肉体において現れるためです」(同8–11節) と記しています。
2.「ひとり子としての栄光……この方は恵みとまことに満ちておられた」
「私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから来られたひとり子としての栄光である」(14節) と描かれていますが、「ひとり子」とは「ただひとり生まれた方」という意味の御父との一体性を表わします。
しかもその「栄光」とは、「雲の柱、火の柱」という驚異ではなく、「恵みとまことに満ちておられた」という神のご性質でした。
かつて、モーセが頑ななイスラエルの民を導くことを恐れ、「どうか、あなたの栄光を私に見せてください」(出エジ33:18) と願った時、神はモーセを「岩の裂け目に入れ」(同33:22) ながら、通り過ぎる時「主 (ヤハウェ) は、あわれみ深く、情け深い神、怒るのにおそく、恵みとまことに富み……」(同34:6) と宣言されました。
イエスが「恵みとまことに満ちておられた」とは、彼こそが、神の真の栄光を見せてくださったという意味です。
「恵み」はヘブル語の「ヘセド」に由来し、しばしば「変わらない(揺るがない)愛」とも訳され、相手の不真実にも関わらずご自分の約束を守り通すという「契約の愛」です。
また「まこと」はヘブル語の「エメット」で「アーメン」と同じ語源です。これは偽りのないという意味です。実際、キリストに現わされた「栄光」は、ご自身のいのちを犠牲にしてまで頑なな民を愛し抜く姿です。それは放蕩に身を落した自分の子を立ち直らせようと、いのちさえ投げ出す覚悟を持つ父親の姿です。それは愛のゆえに傷ついている姿です。
16節の「私たちはみな、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた」とは、やみに満ち、滅びに向かっていた私たちのうちに、キリストの一方的な恵みが無尽蔵に注がれ、心の奥底から造り変えられる様子を表わしています。
ただ、その際、「この方を受け入れる……その名を信じる」(1:12) という私たちの側の応答が必要です。神は人格の主体性を尊重され、心をこじあけたりはしません。
しかし、主は「わたしを信じる者は……その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになります」(7:38) と、ご自身の無尽蔵の恵みを受け入れる者が、さらに無尽蔵の恵みを注ぎ出すと約束されました。
17節では、「律法はモーセによって与えられ、恵みとまことはイエス・キリストによって実現したからである」と、イエスという名がここで初めて登場します。それはイエスがモーセよりも偉大な方であることと、律法の限界を示すためでした。
モーセは神のことばを取り次いだ者でしたが、やがて「ことば」だけが一人歩きして、民を生かす代わりに苦しめるようになりました。それに対して「ことば」が「人(肉)」となったことで、ご自身の身をもって優しく「神を説き明かす」ことができました。
その中心こそ、律法の本来の目的であった神の「恵みとまこと」でした。つまり、律法は人間をさばく基準である前に、神の愛の現れなのです。
3.「ひとり子の神が、神を説き明かされた」
「いまだかつて神を見た者はいない。父のふところにおられるひとり子の神が、神を説き明かされたのである」(18節) という表現には、人となる前のイエスが、なぜ、「ことば」として描かれたかの意味が込められています。
それは、神の「ことば」が神の本来の意図とは異なった意味で理解されるようになっていることを正すために、神の「ことば」ご自身が「人となって」、目に見えるイエスという人格の態度や行動をとおして神のみこころを示してくださったというのです。つまり、私たちはイエスをとおして「神を見る」のです。
確かに神はモーセを通して律法を与えた時、イスラエルの民を偶像礼拝の民の悪い習慣から聖別するため「聖なるものと俗なるもの、また汚れたものときよいものを分け(区別す)る」(レビ10:10) ことを教えましたが、イエスの時代には、残念ながら、それが自分たちの枠からはみ出た者を排除する規定に用いられていました。
それに対しこの福音書では、はみ出し者とイエスとの出会いに焦点が当てられています。それはたとえば、人目を恐れ、夜陰にまぎれてイエスの教えを乞いに来た律法の教師ニコデモ、昔五人の夫を持ち、今は夫ではない者と同棲しているサマリヤの女、迷信的な言い伝えに騙されて38年間を無駄にしたベテスダの池の病人、姦淫の現場で捕えられたという女、罪の結果で盲目に生まれついたと見られていた一人の盲人、死んで四日もたったラザロ、三百デナリの香油を一度に使い切ったベタニアのマリア、そして最後に、イエスの墓の前でたたずんで泣いていたマグダラのマリアなどとの出会いです。
イエスは一人ひとりに、どれだけ誠実に対応していたことでしょう。主には、目の前の一人が常に大切でした。
一方で日本の古事記にも、人を辱め、排除することへの警告が描かれています。
天から降臨したニニギが山の神の娘のコノハサクヤノヒメを見初め、結婚を申し出たところ、山の神はイワナガヒメという非常に醜い姉を添えて嫁入りさせます。何となく聖書でのラケルとレアの物語に似ていますが、ニニギの場合は醜い姉を追い帰してしまいます。
山の神とイワナガヒメはひどく辱められたと怨み、呪いが下ります。姉は岩のように長い寿命の、妹は木の葉が咲くような繁栄の象徴でしたが、それ以来、天の御子は死に支配されるようになったというのです。そこには、人を辱め、排除することへの警告も描かれているのです。
確かに日本の文化は、何よりも調和を重んじます。聖徳太子に由来する十七条の憲法の最初には、「和を以(も)って貴(とうと)しとなし、忤(さから)うこと無きを宗(むね)とせよ……上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん」とあります。
これは天皇を中心に人々が調和して行くなら国が繁栄するという教えです。しかし、和を大切にしたはずの国が一致団結して朝鮮半島から中国に攻め入ったことや、戦後の政府が一致団結して原発推進政策に向かったことを忘れてはなりません。
残念ながら日本の和は、ブレーキの利かない動きの源にもなります。
日本の神話では善悪の基準が曖昧で、乱暴な神々が崇められたりしますす。カナンの宗教と同じく多産と豊穣をもたらす神々が崇められます。
日本では今も、唯一神信仰が争いを引き起こすなどという観念が大勢を占めています。しかし、日本の何よりの弱さとは、永遠の価値観につながるような長期的なビジョンを示すことができないことにあります。それは善悪の基準がないからです。
聖書が語る神の御子の受肉、それは天を支配する永遠の真理が、私たちの世界を内側から造り変えるという動きの始まりです。
しかし、真の神の「ことば」は人となることで、真の神のみこころを明らかにしてくださったのです。
アタナシウスは、キリストがローマ帝国にもたらした変化を、「十字架のしるしによってあらゆる魔術は終わりを迎え、あらゆる魔法も無力にされ、あらゆる偶像礼拝も荒廃させられ、放棄され、非理性的な快楽は終わりを迎え、すべての人は地上から天を見上げている」と証しています。
キリストのすばらしさが明らかになるにつれ、人は、自然に、偶像礼拝や魔術に見向きもしなくなって行ったのです。
そればかりか偶像礼拝では「戦いの神」や「快楽の神」が人々を戦いや無軌道な性の快楽に向かわせましたが、当時の人々は、「キリストの教えに帰依するや否や、不思議なことに、心を刺し貫かれたかのように残虐行為を捨て……平和と友愛への思い」を持つようになり、また「貞節とたましいの徳とによって悪魔に打ち勝つ」というように、生き方の変化が見られたというのです。
刑罰の脅しを含む新たな規範によってではなく、キリストの愛が迫ってきた結果として人々の生活が変えられたのです。
イエスは世界の価値観を変えました。イエス以外の誰が、社会的弱者や障害者に人間としての尊厳を回復させ、また、結婚の尊さや純潔の尊さを説いたことでしょう。イエスの教えがなければ天皇家が子孫断絶の危険まで冒して一夫一婦制を採用することはなかったことでしょう。主の教えなしには、近代医療の原則や福祉制度は生まれませんでした。
現代の日本は、当時のローマ帝国などに比べ、倫理的な価値観からすれば、驚くほどにキリスト教化されています。
現代社会で、ローマ帝国時代ほどにクリスチャンの生き方が目立つことがないのは、皮肉にも、イエスの価値観を多くの人がすでに知るようになり、それが常識となったためとさえ言えましょう。
私たちは、自分の生き方が変わらないことに絶望することがあるかもしれません。しかし心配する必要はありません。私たちの内に住んでおられるキリストの霊は、聖霊と呼ばれるように、私たちを神の聖さにあずからせてくださいます。
汚い「飼い葉桶」の中に生まれたイエスは、あなたをご自身に似た者に必ず造り変えると約束しておられるからです。イエスの御名があがめられるところでは、自然に、偶像礼拝や不道徳は力をなくして行きます。
不条理や不正と戦うのではなく、キリストが世界に知られるようになることこそが大切なのです。キリストの愛を味わい、それを証しすることによって自分も世界も変えられるのです。
「ことばが人となられた」のは、私たちが神の愛とあわれみを知ることができるようになるためでした。そして、「ことばの受肉」を信じる者は、腐敗から不滅へ、死からいのちへと移されるのです。
二千年前に、私たちの創造主が、滅び行く人間となられたのは、「私たちがみな、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられてゆく」(Ⅱコリント3:18) ための第一歩でした。
日本の文化を否定するのではなく、私たちこそが多くの日本人が無意識のうちに天皇に期待しているような平和の礎になることができることを覚えるべきです。なぜなら、私たちのうちに「太陽の創造主」ご自身が宿っておられるからです。
1653年にドイツのパウル・ゲルハルトが書いたクリスマスの黙想の歌「飼い葉桶の傍らに」では、その1番で、私の心の創造主が飼い葉桶に眠っている、その傍らに自分が立っていることをイメージしながら、その不思議を歌っています。
2–4番と9番の歌詞を味わってみましょう。キリストの謙遜による癒し、創造の光の内住、計り知れないイエスの栄光、自分の身体をイエスの飼い葉桶とする幸いが歌われます。
讃美歌107番 私訳
- まぶねのかたえに われは来たり いのちの主イェスよ きみを想う
受け入れたまえや わがこころすべて きみが賜物なり - この世にわれまだ 生まれぬ先 きみはわれ愛し 人となりぬ
いやしき姿で 罪人きよむる くしきみこころなり - 暗闇包めど 望み失せじ 光 創(つく)りし主 われに住めば
いのちの喜び 造りだす光 うちに満ちあふれぬ - うるわしき姿 仰ぎたくも この目には見えぬ きみが栄え
ちいさきこころに 見させたまえや はかり知れぬ恵み - 主よ わが願いを 聞きたまえや 貧しきこの身に 宿りたまい
きみがまぶねとし 生かしたまえや わが主 わが喜び